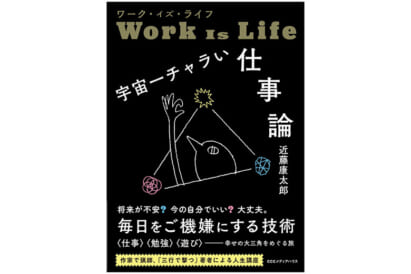一刀両断 実践者の視点から【第673回】
NEWS
家庭訪問の意義
かつてこの時期は当たり前のように行っていた家庭訪問も、今ではすでに過去の行事となってしまった。家庭訪問は、子どもの家庭環境を知るための貴重な機会であり、教師にとっても意味のある時間だった。
自分は訪問の順番をあらかじめ決めておき、次に訪問する家庭の子どもに迎えに来てもらうという形を取っていた。時間が押すと走って移動することもあった。
訪問先では飲み物を出してもらうことが多く、トイレを借りることもしばしばあった。最後の家庭では食事を勧められることもあり、緊張しながらも心温まる、楽しい行事だった。
その後、家庭訪問は希望制となるなど、実施そのものが難しくなっているのが現状だ。「家庭でどのように勉強しているかを見に行くよ」と話しながら、自然に家庭の様子を知るようにしていた。
最近では「家庭訪問」とは言わず、「家庭確認」と呼ぶらしい。ある担任は「外から見るだけでは、その家庭のことは覚えられない」と言っていた。
こうした時代の変化は本当に良いことなのだろうか。個人情報やプライバシーへの配慮は確かに大切だが、その中でも状況を丁寧に把握し、子ども一人ひとりに合った対応をしていた記憶がある。
(おおくぼ・としき 千葉県内で公立小学校教諭、教頭、校長を経て定年退職。再任用で新任校長育成担当。千葉県教委任用室長、主席指導主事、大学教授、かしみんFM人生相談「幸せの玉手箱」パーソナリティなどを歴任。教育講演は年100回ほど。日本ギフテッド&タレンテッド教育協会理事。)