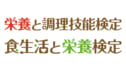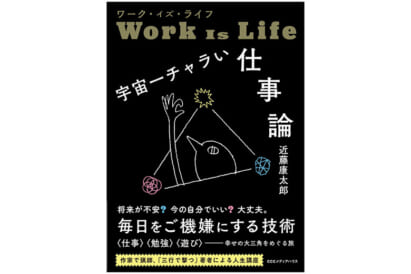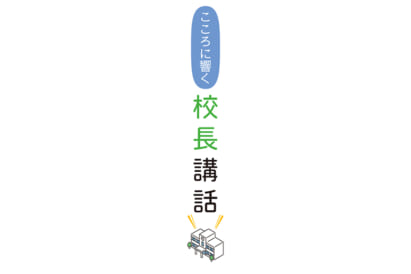「会計」を通して社会の見方を育む社会科教員向けセミナーを開催~「会計」を取り扱った実践事例を紹介~
9面記事
2024年8月7日東京会場の基調講演
「会計情報の活用」を中学校の授業で取り扱う方法や実践事例を共有する教員向け研修「『会計』を通して社会の見方を育む社会科教員向けセミナー」(主催=日本公認会計士協会、日本教育新聞社)が、前年度に引き続き、2024年度は全国4都市で開催された。この研修会では、同協会が提供している教材「『会計情報の活用』教員のための授業実践ガイドブック」(以下、「授業実践ガイドブック」)等を活用した各地域の教員による実践事例が紹介された。中学校学習指導要領解説に明記された「会計」を学校ごとの教育課程にどのように位置づけ、生徒の能動的な学びにつなげているかについて、各会場での講演の模様を報告する。
全会場 基調講演
中学校社会科における「会計リテラシー」の取り扱い
樋口 雅夫 玉川大学教育学部教育学科 教授

樋口 雅夫 教授
基調講演では、玉川大学樋口雅夫教授が「中学校社会科における『会計リテラシー』の取り扱い」と題して、会計教育の意義を解説。教材の活用方法や、次期学習指導要領改訂に向けての展望を語った。
現行の学習指導要領解説に「企業会計」・「会計情報の活用」が記載された背景には、成年年齢18歳への引き下げや、AIの進化による社会の変化がある。会計情報の活用を通じて、(1)企業を経営・支援することへの関心を高める(2)利害関係者への適正な会計情報の提供と活用の理解(3)公正な環境での法令に則った財・サービスの創造の仕組みの理解の3点が目標とされている。
樋口教授は、生徒が会計を「自分ごと」にできる課題解決型の授業を実践するには、学校と専門家が協働することが重要だとして、日本公認会計士協会が開発した教材を取り上げた。
2024年12月には、中教審へ次期学習指導要領改訂に向けた諮問があり、樋口教授は「会計という社会とつながる内容を扱い、子ども自身の夢の幅を広げる教育が求められている。次期学習指導要領改訂ではこうした点も一層考慮されることを期待したい」と結んだ。
日本公認会計士協会の取り組み紹介

梅木 典子 常務理事
全セミナーの最後には、日本公認会計士協会の梅木典子常務理事が登壇し、協会が進める活動について説明した。同協会は、会計教育の推進において「学校教育の支援」を主要な柱に据えており、具体的な取り組みとして、「『会計情報の活用』授業支援パッケージ」や「『会計情報の活用』教員のための授業実践ガイドブック」を作成し、ウェブサイトで公開していることを紹介。
また、中高生向けに制作された会計リテラシーを学べる動画「一言のシン」や、公認会計士が講師となって学校で授業を行う「会計教育講座」も展開している。
これらの取り組みに関する問い合わせは、協会本部および全国16地域に設置された地域会で対応している。
※「『会計情報の活用』授業支援パッケージ」「『会計情報の活用』教員のための授業実践ガイドブック」は、下記URLからダウンロードができます。
https://jicpa.or.jp/about/activity/basic-education/tools.html
2024年8月7日 東京会場 授業実践発表
損益計算書からPB商品の安さの秘密を探る
行壽 浩司 福井県美浜町立美浜中学校 教諭

「従来までの中学校公民的分野でおこなわれている経済教育は、会計教育によってブラッシュアップされるべき」。そう語る行壽氏は、その可能性を探る実践として「なぜプライベートブランドは安いのか?」というテーマを取り上げた。
プライベートブランド(PB)商品とは、小売店などの自主企画商品を指す。一方で、ナショナルブランド(NB)はメーカーが展開する全国的な商品だ。授業では、生徒たちが飲料や食品などのPB商品と、NB商品の製造元が同じ企業であることを確認し、同じ企業が製造しているにも関わらず、PB商品の価格が安い理由を考察した。
生徒たちは損益計算書を使い、「人件費」や「水道光熱費」など、企業が商品を製造・販売する際に必要な諸費用について学んだ。その過程でPB商品の価格が安い理由として「広告宣伝費の削減」という仮説にたどり着いた。広告費を抑えることでコスト削減につながり、その結果、消費者に安価な商品を提供できるという仕組みだ。
行壽氏はこの授業を「流通の合理化」の一例として位置づけ、小単元「資本主義経済と企業の生産活動」の理解を深めるために活用した。「損益計算書を用いることで、生徒自身が主体的に知識を獲得できる点が大きな利点」と述べ、生徒たちに経済活動の仕組みを実感させるだけでなく、自ら考える力を育む教育として有効だとした。
会計情報を活用して「投資の注意点」を考える
阿部 哲久 広島大学附属中・高等学校 教諭

阿部哲久氏の授業では、中学3年の社会科で経済の単元を終えた後、「金融の仕組み」をテーマに、学んだ知識と実際の社会で行われている経済活動のつながりを意識することを狙いとして、授業を行った。
生徒に投資についてのイメージを尋ねたところ、「関心がある」という意見から「怖い」という意見まで幅広い反応があった。そこで、「投資は金融の一部であり、金融とはお金が余っている人から必要としている人への融通である」という教科書の定義を基に、教材「授業実践ガイドブック」を活用して具体的な事例を用いて理解を深める工夫をした。
例えば、「車を現金200万円で一括購入する場合とローンを組んで購入する場合、どちらが得か」といった事例では、ローン購入をして、現金を投資に回しローンの利子以上の利益を出せれば得である、という考え方があることを解説。また、「年収10億円と資産100億円、どちらがお金持ちか」という問いでは、フロー(収入)とストック(資産)の違いに基づき、直接比較できないことを生徒たちに紹介。さらに二つの企業の貸借対照表を比較して業種を当てるクイズを実施し、決算書の読み取り方を解説した。
こうした具体例を通じて、生徒は金融の役割について理解を深めるとともに、決算書の読み方について学ぶことで会計情報の重要性への認識を高めたという。
2025年2月1日 札幌会場 授業実践発表
会計教育を通して起業家精神を育む
小谷 勇人 埼玉県春日部市立武里中学校 教諭

小谷氏は、模擬的な起業体験と会計教育を組み合わせ、生徒が主体的に会計スキルや経済の仕組みを学び、チャレンジ精神や自己肯定感を高める授業を行った。
授業では、生徒たちが架空の会社を設立し、経営者や会計担当などの役割を分担して活動を進める。具体的には、商品の企画から販売戦略の立案、収支報告書の作成までを体験することで、経済活動の流れを実感しながら学ぶ仕組みだ。
企業の社会的責任(CSR)を学習する場面では、企業会計や会計情報の活用の必要性について取り上げた他、SDGs(持続可能な開発目標)についても議論するなど、単なる利益追求だけでなく社会課題への意識を育む内容として取り扱った。その上で、実際に自分たちの会社で、どのように企業の社会的責任を果たすかについて考えさせた。
会計担当の生徒からは「利潤につなげるには人々の信用が大事」など、会計を担当したからこその感想が寄せられた。授業内では、生徒が空き家問題への解決策を提案する「民泊のフランチャイズ経営」など、現実社会に積極的に関わろうとする姿勢も見られたという。
小谷氏は今後、この取り組みをさらに発展させるべく、1人1台端末を活用しメタバース上での起業体験や国際的な視点を取り入れ、企業とタイアップした授業設計を目指している。
粉飾決算から会計情報の重要性を学ぶ
兼間 昌智 札幌大学 非常勤講師

中学生に会計の重要性を理解させるためには、「市場経済の基本的な考え方を身につけた上で、模擬的な企業経営に役立つ学習を組み立てる必要がある」と兼間氏は語る。
提案された授業案の導入では、2013年の人気テレビドラマ『半沢直樹』のストーリーを紹介し、「粉飾決算」について説明。その後、過去に実際に起きた日本企業の不正会計事件を紹介することで、会計の重要性について考えるきっかけを示した。
次に、会計情報と企業の経営について学ぼうと題し、貸借対照表や損益計算書の基本的な仕組みについて提示。実際に、パン屋の1日の損益計算書を作る活動の中では、家賃などの固定費は、決まった価格を提示した上で、「1個あたりの材料費を130円として1個の価格と販売数がどのくらいで黒字になるか」を考える課題をあげた。
この活動のポイントでは、販売する町の規模や人口、店舗の1日あたりの販売数などの条件を教員が提示し、生徒が現実的な視点から考えやすくなるよう工夫することが大事だと話した。「企業会計」のイメージをつかませた後、改めて会計情報公開の意義とともに、「企業会計」は企業の経営成績と財務状態を表しており、法律で開示が義務付けられていることをおさえる授業案としている。
2025年2月8日 大阪会場 授業実践発表
模擬「決算報告」をゴールにおにぎり屋を経営
阿部 孝哉 大阪府吹田市立豊津中学校 教諭

以前からおにぎり屋の開業を題材にした起業体験授業を実施している阿部孝哉氏。今回、より現実社会に近い内容へと改良する材料として「決算報告」を実施する新たな実践を行った。
最初に、「メニュー1種類のみのおにぎり専門店を起業する」という条件のもと、生徒たちが個人で起業企画案を作成。食材費や什器(じゅうき)、テナント料など、開店に必要な費用を概算で算出した。
その後、中学1年生がウェブ開発で起業した例を取り上げ、株式会社の仕組みについて学習。また、教材「授業実践ガイドブック」を活用し、価格設定の方法や決算報告の意義について理解を深めた。さらに、いくつかのクラスで「おにぎり」の人気投票を行い、その結果を売上としてシミュレーションを行った。
最後に、決算報告会を実施。生徒たちは1年間のおにぎり販売の利益をシミュレーションし、損益計算書や貸借対照表を作成。その後、それらを基に決算報告資料を作り、数名の班の中で発表を行った。
この授業を通じて、生徒は実際の企業が行う決算報告のプロセスを追体験し、明確な目的意識を持って活動に取り組むことができたという。阿部氏は、「今後は『金融』や『流通』の視点も取り入れた実践を工夫していきたい」と意欲を語った。
中学1年生の地理で会計教育を取り入れる
小川 駿也 福井県立高志中学校 教諭

小川氏は中学1年の地理的分野の授業で会計教育を取り入れる実践を行った。通常は3年の公民的分野で扱う会計の要素を、アジア州の学習に組み込んだ画期的な試みだ。
授業は2段階で構成した。まず生徒たちは身の回りの製品がどこで生産されているかを調査し、多くの製品がアジアで生産されている理由を探った。グループ活動を通じて「人口が多い」「賃金が安い」「資源が豊富」などの特徴を見出した。
次に「世界の工場であるアジアのどこで起業すると良いビジネスができるか」という課題に取り組んだ。その前段階として、教材「授業実践ガイドブック」を活用し、パン屋の経営シミュレーションを実施した。生徒たちは社長、営業宣伝担当、財務担当などの役割を分担し、オリジナルのパンを企画・価格設定した。
このシミュレーション体験を踏まえ、各グループはアジアの国々の特色を活かした起業プランを考案。「人口増加に対応した住宅提供会社(インド)」「鉄道敷設事業(フィリピン)」「スタディツアーと防災グッズ販売(フィリピン)」などのアイデアが生まれた。
小川氏は「中1段階では価格設定や利益追求の考え方の理解は難しい面もあったが、この経験が中3での本格的な会計学習の基礎になる」と振り返る。また「買い物をする際の視点が広がったのではないか」と、実生活への意識の変化にも期待を寄せている。
2025年3月1日 福岡会場 授業実践発表
パン屋経営シミュレーションで学ぶ企業活動
岩野 清美 福岡県北九州市立板櫃中学校 講師

岩野氏からは、公民的分野「私たちと経済(1)市場の働きと経済」の特設単元として、「パン屋さんを経営しよう」というテーマで、企業活動における会計の重要性を体験的に学ぶ実践が紹介された。
授業は2時間構成で実施。第1時では、生徒たちが4人1組のグループでパン屋を開業し、材料費や価格設定を考えながら商品開発を行った。各班は自分たちのパンの特徴や価格をアピールし、クラスメイトが顧客となって購入する活動を通じて、企業活動の基本を体験した。
第2時では、売上結果を基に利益計算を行い、赤字・黒字の要因分析を実施。さらに「2店目を出店するための資金調達方法」について考える活動へと発展させた。銀行融資、クラウドファンディング、株式発行などの選択肢から最適な方法を議論し、企業の資金調達と会計情報公開の意義について学んだ。授業後の振り返りでは、経営の難しさや、原価と売値のバランスの重要性など、生徒たちの気付きが増えたことが報告された。
岩野氏は「経営状況の把握や、事業改善に会計が必要だと生徒たちは理解した。だが、適正な情報開示の意義を、嘘をついてはいけないという社会通念にとどめず、社会の仕組みに関連付けて理解させることには課題が残る」と語っている。
会計情報を学び実際の企業に事業展開を提案
山本 翔 熊本大学教育学部附属中学校

山本氏は、公民的分野で消費生活、生産労働、市場経済の仕組みを学んだ後に「会計」の学びを導入するのが適切だと考え、授業は「私たちは市場経済とつながっていると言えるのか」という問いから始めた。
生徒たちは最初、消費者として市場経済とつながっていると考えていたが、大人として社会へ出るには生産者や経営者の視点が欠けていることに気付いた。この気付きを受けて、山本氏は会計情報の学習を提案し、「会計情報を学習することで、私たちは市場経済とよりよくつながることができるのだろうか?」という追究課題を設定した。
授業では貸借対照表や損益計算書の基礎を学んだ後、生徒たちはシェアサイクル事業を展開する「チャリチャリ株式会社」の財務諸表を分析。また、同社の家本賢太郎社長を招いて講演会を開催し、熊本で事業を発展させるための計画立案に挑戦した。
生徒たちは熊本市の交通渋滞問題を踏まえ、ポート設置や定額プランなどのアイデアを提案した。さらに、同社の会計情報を根拠としたプレゼンテーションを行い、家本社長からのフィードバックや、質疑応答を通じて企業経営への理解を深めた。
この実践について、生徒たちからは「会計情報を活用することで今までよりも圧倒的に根拠のあるプレゼンが作れた」との感想があった。山本氏は、「生徒たちの視野が広がり、自分たちの提案が社会に影響を与える可能性があると実感できたことが最大の収穫」と評価している。