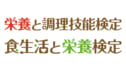自立と自律 未来を育む成年年齢引き下げと教育の役割
18面記事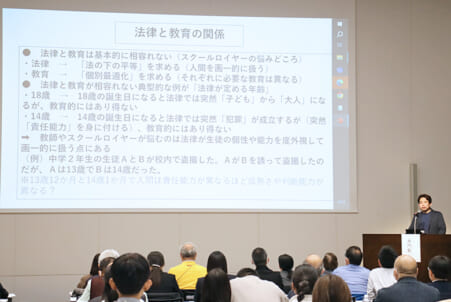
令和4年4月の改正民法施行により成年年齢が18歳に引き下げられて丸3年。日本教育新聞社は3月16日、東京都千代田区のイイノホール&カンファレンスセンターで「みんなで学ぶ18歳成人・18歳成人オンラインフェアvol.3~社会で自立して生きていくために必要な力とは?」をテーマにセミナーを開いた。同月29~31日には会場開催の模様をオンラインで配信。各専門家らが18歳成人をテーマに多角的な視点から話し合った。
後援=文部科学省、法務省、警察庁、消費者庁、金融庁、こども家庭庁、全国高等学校長協会、全国都道府県教育委員会連合会、東京都教育委員会、日本私立中学高等学校連合会、日本私立大学協会、日本PTA全国協議会、全国高等学校PTA連合会(順不同)
基調講演 スクールロイヤーと高校教師の視点から考える18歳成人の時代
弁護士、兵庫教育大学教授、私立中高一貫校社会科教諭 神内 聡氏

弁護士・大学教授であり、現役の高校教員(非常勤)も務める神内氏がまず問題視したのは、「18歳成人」の制度的な複雑さである。具体的には、法律の世界では「法の下の平等」が求められるのに対し、学校教育では生徒一人ひとりに合わせた「個別最適な指導」が建前とされている。この差異・食い違いが、スクールロイヤーと教員の双方にとって悩ましい問題になるという。
現実の高校3年生の教室では、18歳に達した生徒とそうでない生徒が混在している。「18歳の誕生日を迎えると、法律上は突然『子ども』から『大人』になるが、これは教育的にはありえないことだ」と神内氏は指摘する。まず、この点がそれぞれの立場で戸惑う大きな要因となる。
現実に起こりうる問題として、神内氏は以下のような点を挙げた。
・18歳になると「保護者がいなくなる」生徒が出てくること。これは進路決定や生徒指導などに影響を及ぼす可能性がある。
・私立高校の場合、入学時に生徒と保護者の連名で誓約書を提出することが多いが、18歳成人によってこの法的効力がどうなるかが問題となる。
・法律上は教員と同じ立場(成年者)の生徒が存在すること。これにより、成年となった高校生が教員や学校に対して訴訟を起こす事態も起こりうる。例えば、校則の違法性を訴えるなど。
生徒が賠償責任を負うような事態について、神内氏は「当然、18歳の生徒にそのような責任を負うことは難しいと考えづらく、今後の裁判例を待つことになるが、被害者救済の観点からは、保護者でなくなった者にも監督義務に基づく責任を継続させるのではないかと考えられる」と述べた。
自治体講演 東京都教育委員会
東京都のキャリア教育の取組について

「高校段階は自分の将来や生き方、進路を考え、社会でどう生きていくかという課題に出会う時期であり、将来のキャリア形成を自分で考え、生活することが重要です」。
こう切り出した東京都教委の担当者は、都立高校で行われているキャリア教育の内容を紹介。
(1)東京都独自の教科「人間と社会」
(2)都立高校生の社会的・職業的自立支援教育プログラム事業
(3)高大連携事業
―の3点を挙げた。
このうち、高大連携事業では、各大学の特色を生かしたゼミ形式の探究活動等を通して、生徒たちは、大学進学の目的を明確にしたり、大学生活や大学卒業後を意識し、将来について考えるきっかけとしている。
企業講演(1)日本FP協会
FPが教える お金との上手な付き合い方

日本FP協会は、パーソナルファイナンス教育インストラクターの髙木典子氏が講演を行った。髙木氏は、お金との上手な付き合い方を「自分のやりたいことやなりたい自分を想像し、それを目標に計画を立てること」と定義し、現実的に起こりうることとして、重い病気で働けなくなること、交通事故を起こすこと、住宅を購入することなどを挙げ、「人生における予期せぬ出来事やライフイベントに備えた資金準備も必要」と述べた。
人生設計のためのテンプレートとして、「10年後の自分を思い描いてみよう」「30年後はどうだろう」といったフレーズを提示し、30年後の自分を想像する際には、自分の親の姿を思い浮かべることが効果的だと説明。学校教育では税金や社会保険の仕組み、とりわけ公的年金や医療保険制度について教えてほしいと求めた。
企業講演(2)日本税理士会連合会
なぜ今、租税教育が必要なのか—税理士が行う租税教育について—
日本税理士会連合会常務理事・租税教育推進部長 菅原 一朗氏

「租税教育とは何か」と問いかけるように講演した日本税理士会連合会の菅原一朗常務理事は、その答えを「租税に関する意義・役割・機能・仕組み等の租税制度を理解するとともに、申告納税制度の理念や納税者の権利及び義務を理解し、社会の構成員として正しい判断力と『健全な納税者意識を持つ』国民を育成すること」と述べた。
さらに、「納税者意識とは、主権者として国や地方公共団体に関心を持ち、正しい知識を持って税金の使われ方を注視すること」と説明した。その意識が欠如すると、選挙投票率の低さや公債残高の多さといった形で現れると指摘し、租税教育の必要性を述べた。
講演【非行防止・闇バイト】警察庁
少年を犯罪の加担者、被害者にさせないために
警察庁生活安全局人身安全・少年課少年保護対策室長兼児童性被害対策官 前澤 綾子氏

警察庁少年保護対策室の前澤綾子室長は、「少年を犯罪の加担者、被害者にさせないために」を主題に話した。「闇バイト」は高額報酬を謳うが、実際は支払われない場合が多いと指摘し、「闇バイト」の特徴や実態を知り、「闇バイト」募集に気付けるようにするのが対策の第一歩になるという。「闇バイト」であると気付いた時点で、一人で悩まずすぐに周囲に相談してほしいと語った。
また、タイ・ミャンマー国境での高校生監禁事件にも触れ、オンラインゲームを通じた詐欺グループとの接触の危険性を訴えた。
特に、オンラインゲームでの交流により、犯罪者が巧みに信頼関係を築き、少年たちを犯罪に引き込むこともあるため、注意してほしいと訴えた。
講演【契約】契約のキホン
弁護士 菊間 千乃氏

菊間千乃弁護士ははじめに、未成年者が行った契約の取り消し規定について焦点を当てた。成年年齢引き下げにより「何かあったときに、(契約を)取り消してもらえる、ということが通用しなくなる。自分の子どもや生徒は大丈夫と思っていても、巻き込まれるケースが増えている」と解説した。
契約の範囲は広範に及ぶという。菊間氏は、契約の成立と方式を定めた民法522条を挙げ、「契約の成立要件は、申込と承諾の意思表示の合致なので、契約書という形になっていなくても、口約束やメールでも契約は成立していると判断される可能性はある」と説明。「安易に自分の意図しないことを承諾するようなメールを送らないように」と注意を促した。
菊間氏は、男女間で300万円を「貸した」「いや、自分に投資してもらった」と主張が食い違った事例を紹介し、トラブルを防ぐために契約書を作成すべき理由を説明した。
さらに、美容医療や定期購入、訪問販売などの消費者トラブルの事例を挙げた上で、契約で騙されないための二大ポイントとして「その場で決めない」「少しでも疑問に思ったら、誰かに相談する」の2点を示しまとめた。
講演【消費者教育・授業】
自立した消費者に必要な力と学校での取り組みについて
法政大学大学院政策創造研究科准教授、(公財)消費者教育支援センター理事首席主任研究員 柿野 成美氏

法政大学大学院の柿野成美准教授(消費者教育支援センター理事・首席主任研究員)は、成年年齢引き下げの前年に高校1、2年生を対象に消費者教育支援センターなどが実施した調査結果を紹介。男子の最多回答は「特に何も思わない」の38・7%だったのに対し、女子は「消費者被害にあうかもしれないと不安に感じる」が32・8%で最も多かったという。
柿野氏は「不安に思っている人に対し、『気を付けろ』『こんなアプローチがある』と注意喚起するだけでは、自立した消費者育成に繋がらないのではないか」と問題提起した。
好ましい授業実践例として、埼玉県で県立高校と大学生が参加した取り組みを挙げた。県内企業の不当表示広告を調査して県消費生活課に報告するという内容。生徒はスマートフォンなどで日常的に企業の広告を目にする中で、「これはおかしいのではないか」と感じた広告を報告した。県は生徒から寄せられた情報を基に事業者へ行政措置を行う。実際に、行政による事業者への指導に繋がることで、生徒は社会の改善に貢献しているという実感や自己効力感を得られるという。
柿野氏は「実際に行動に移し、実践的能力を育んでいくというところにどうやって持っていくかが消費者教育の課題になっている」と述べた。
パネルディスカッション
18歳成人 成年年齢引き下げに伴う問題について
【参加者】神内 聡氏、菊間 千乃氏、柿野 成美氏

パネルディスカッションの様子
パネルディスカッションでは参加者から寄せられた質問に、パネリストが回答した。進行役は菊間氏。
このうち、市議会議員からは「管理されるばかりではなく、ルールをつくっていくマインドに変わることで得る力もある。成人としての責任ばかりではなく、得られる力についても教えて」という質問が出た。
柿野氏は「例えばブラック校則を見直していく取り組み。校則、変えていいんだ、ということになっていけば、18歳の自立した大人になっていくときに身に付けていきたい社会の形成者としての力に結び付くだろう」と述べた。
他方、神内氏は「生徒によっては、厳しい校則のままでよいという声もある。ルールを緩くしたら居心地がよくなるかと言えば、かえって悪くなる場合もある。ともあれ、ルールは変わっていくものだとか、考え見直していくものだと気付くきっかけにはなる」と応じた。
これらに対し、菊間氏は「法律も変えることができるし、変えるべきもの」という見方を示した。
締めくくりに、高校生・教員へのメッセージとして神内氏は、教員として卒業生が年齢を重ねていく姿に接した経験に触れ、「18歳、今しかない。若い活力でいろいろチャレンジしてほしい」と激励を贈った。
柿野氏は、「子どもたちに夢を与えられるよう、18歳成人に向けた教育を進めたい」と抱負を披露。菊間氏は「成人になったからといって急に社会に放り出されるわけではない。分からなかったら聞いてください」と呼びかけた。