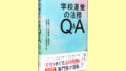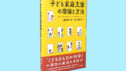「嘘をつく」とはどういうことか 哲学から考える
19面記事
池田 喬 著
谷川俊太郎の詩をテキストに
「嘘も方便」「嘘つきは泥棒の始まり」「嘘から出た実」「嘘八百」。嘘にまつわる慣用句は多数あり、嘘のマイナス面とプラス面を表現している。それは、嘘が私たちの生活に密着したものだからだろう。私たちは他者とともに暮らす中で、嘘をついたり、嘘をつかれたりする。私たちは、経験的に嘘について理解しているといえるだろう。
それでは、「嘘とは何か」と問われたときに、答えることができるだろうか。本書は、この問いを哲学的に解き明かそうとしたものである。本書は、全部で3章から成り、嘘についての哲学説が具体的な事例に基づいて説明されている。さらに、人間関係やコミュニケーションの中で展開される嘘について、哲学的理解が試みられている。谷川俊太郎の「うそ」についての詩の紹介から始まり、丁寧で綿密な哲学的議論を経て、「うそ」の詩の理解に戻る、という構成になっている。これは、哲学と生活、人生との結び付きを示すという点で巧妙であり、絶妙である。
「嘘をつくことは悪いことだ」と一言で片付けてしまってはいけない。言葉を話す動物としての人間が、他者とのコミュニケーションを通じて、自らの内面世界をつくり上げていくには、「嘘をつく」という行為形式が不可欠である。本書をじっくり読むことで、「嘘をつく」ことが有する豊かさを実感できるだろう。
(990円 筑摩書房(ちくまプリマー新書))
(都筑 学・中央大学名誉教授)