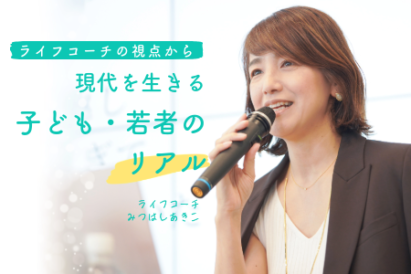教員給与特別措置法、本会議質疑の模様は
NEWS教員給与特別措置法(給特法)の改正案は、10日の衆院本会議で審議入りした。阿部俊子文科相による趣旨説明の後、与野党からの質疑が行われたが、各党は何を問い質したのか。主なものをまとめた。文部科学委員会では16日から実質審議が始まる予定だ。
今枝宗一郎氏(自民)―今回の法案では、教師の勤務環境の改善を図るとしているが、教育の質向上にはどうつなげるのか。
文科相 教師を取り巻く環境整備を進めた先に目指すのは、学校教育の質の向上を通じた全ての子どもたちへのより良い教育の実現。働き方改革により創出した時間を活用し、教師が自らの人間性や創造性を高め、高い専門性を最大限に発揮して教育活動を行うことができるようにする。働き方改革や処遇改善を通じて教師に多様な人材を確保し、質の高い教職員集団の実現を図ることにもつながる。
―昨年末の文科相と財務相での大臣合意の内容を財務省として確実に実施していくことを求める。大臣の決意は。
財務相 大臣合意に基づき、所管である文科省と連携して着実な対応を図る。
浮島智子氏(公明)―都道府県の人事委員会が労働基準監督署のような役割を果たすことになってはいるが現実には十分に機能しているとは言えない。地元の社会保険労務士会などと連携して外部専門家に教員が相談できる体制構築に向けたモデル事業を進めるべきではないか。
首相 教員の人事管理は一義的には教育委員会が担うものであり、政府としても勤務状態等の相談窓口を設置し適切な対応を行うよう促してきた。その際、外部専門家を活用することは相談機能の強化を図る上で有意義な側面をあると考えられるため、御党のご意見も拝聴しながら検討し、必要な取り組みを進めていく。
坂本祐之輔氏(立民)―公立学校教員の時間外労働の上限規制を遵守させるには、監督機能が不十分。給特法下でも健康確保措置や安全配慮義務はある。罰則等を管理職や設置者に課す必要があるのでは。
首相 本来、校長や教育委員会は教師の健康を確保し、安全に配慮する義務を有する。今回の法案では、他の公務員の例を踏まえ、罰則を設けることとはしていないが、計画の策定・公表、計画に基づく実施など、教育委員会や学校が健康確保をする措置を講じる旨を規定しており、これらの取り組みを通じて教師の健康や安全の確保に取り組んでいく。
高橋英明氏(維新)―教育委員会に業務量管理・健康確保措置実施計画の策定・公表、実施状況の公表が義務付けられたが、有効性に疑念。少しで進んでいるように見せるために数値の改ざん・隠蔽につながり、さらなるブラック化を招く恐れがある。
首相 学校が虚偽の勤務実態を記録するようなことがあってはならない。政府としても教育委員会等に対して引き続き指導を徹底していく。
法案では計画の実施状況が不十分な場合の罰則は設けていないが、各教育委員会が自ら定めた計画の実施状況の公表及び首長が設置する総合教育会議への報告を規定しており、こうした仕組みを通じて教育委員会による計画の着実な実施を促していく。
西岡義高氏(国民)―給特法の仕組みと労働基準法の考えで齟齬が生じている。今回の法案でもこの齟齬は残るが、このままで差し支えはないのか。
文科相 給特法と労働基準法の違いについて、給特法は公立学校の教師の給与その他の勤務条件に関する特別法であり、労働基準法等の勤務時間に関する考えとは違いがあるが、今回、給特法等の法制的な枠組みを含め中央教育審議会においても審議し、検討を重ねた結果、教師の裁量性を尊重する給特法の仕組みは現在でも合理性を有しているとの結論に至った。文科省としては今回の法案で導入する仕組みを活用し、働き方改革をさらに加速し、時間外在校等時間の縮減を目指していく。
―次なる教員勤務実態調査の実施の有無とその時期は。
文科相 教員勤務実態調査は、抽出された学校の教師が特定の月において一週間の全ての業務内容を記録するなど学校現場への負担も大きい調査だ。他方、昨今各教育委員会において教師の在校等時間の客観的な記録が徹底されてきたところだ。これらの点を踏まえ、今後は基本的に、毎年度教育委員会に対して実施する調査を通じて全国の教師の時間外在校等時間の状況を適切に把握していく。
大石あきこ氏(れ新)―部活動指導や授業準備、保護者対応などの時間外在校等時間について、厚労省ガイドラインに示す労働時間と認定できる場合があるのではないか。
厚労相 超勤四項目以外の時間外在校等時間が労働時間に該当するか否かについては個別具体的に判断されることだが、労働者の行為が使用者の指揮命令下におかれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる。
田村貴昭氏(共産)―教職員の定数を抜本的に増やすこと、年間授業時数そのものを減らすなど、業務量を減らすべきだが、業務量管理・健康確保措置実施計画の策定を義務付けるのみ。目に見える成果を求めれば、これまで以上に時短ハラスメントなどを招くことにならないか。
首相 校長や教育委員会は、教師の在校等時間を目標とする時間の範囲内にすることのみを目的とするのではなく、把握した状況を踏まえて業務の改善のための措置を講ずることが重要であり、政府としてこうした趣旨を徹底していく。