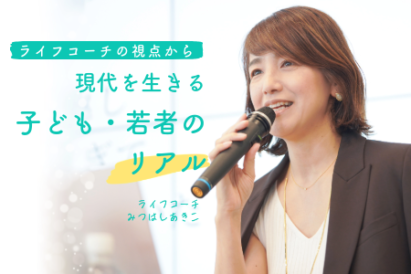「体育」から逃走する子どもたち 「これからの体育(体の教育)」について考える
14面記事
石垣 健二 著
「体でわかる」大切さ指摘
子どもたちに人気のある「体育」という教科から逃げ出す子どもが増えているのではないか、という提起は刺激的である。
「これまでの体育」(第1章)として戦前・戦後の体育の変遷を解説しつつ、体力テストで顕在する「体力低下」への対応や「技能」を中心とした体育の在り方、「思考力・判断力・表現力」を求める授業を第2~4章で取り上げ、その在り方に疑問を呈する。第5章で体育は勝利至上主義の「スポーツ」とどう関わるべきかを語り、第6章に至って「体の教育」を提案。考え方を補強する「付論1」と、「付論2」に瀧澤文雄・千葉大名誉教授の寄稿「賢い[からだ]を育てるために」を収録した。
バスケットボールの練習時、作戦ボードを使いながら子どもたちが話し合い、ボール運びや個々の動き方を改善しようとする授業場面は珍しくなくなった。著者は個の技能の向上を置き去りにした改善に首をかしげる。
「考えると自転車に乗れるようになるか」という著者の問いは分かりやすい。乗り方の習得法はいろいろあるが、自転車に慣れ親しんで乗り方を身に付けていくのが一般的だろう。「『体でわかる』ことは、『頭でわかる』ことで代替し得ない」という運動の授業についての著者の指摘にうなずく方もいるだろう。体育の授業改善には、いろいろなアプローチ法がある。その際、本書が突き付ける課題にどう答えるか。一読してみてほしい。
(2420円 溪水社)
(矢)