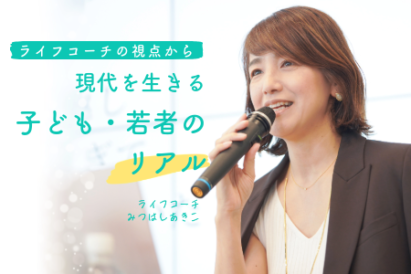教育課題に応え、進化する「学生服」「体操服」
14面記事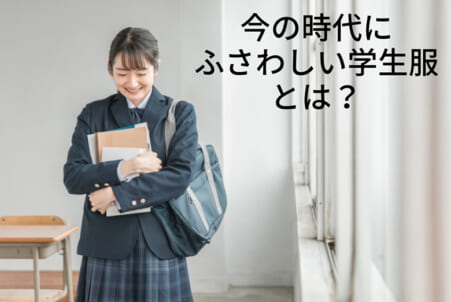
デザイン、スタイル、機能、どれも進化が進む学生服
教育課題に応え、進化する「学生服」「体操服」
グローバル化やテクノロジーの進化により社会構造が大きく変化する中で、学校教育には従来の価値観や枠組みを超えた新たな取り組みが求められている。日本独自の文化として学校像や学生らしさを表現してきた「学生服」も、その役割や目的が多種多様になっており、制服メーカーはこうしたニーズや教育課題に応える商品開発が欠かせなくなっている。ここでは、そのような時代の変化に対応して進化を続ける「学生服」「体操服」の最新動向を取り上げる。
ブレザー化の浸透による差別化がカギ
性差の少ない制服への切り替えが進む
一人一人が違った個性や能力を持つ個人として尊重され、誰もが希望を持って自分らしく生きることができるダイバーシティの実現が望まれる中で、学校教育の現場においても校風や校訓といったものを重視するだけでなく、多様性、公平性といった考えを子どもたちに定着させていく必要がある。
その中で、「学生服」には私立高校を皮切りにLGBTQに配慮したモデルチェンジの波が押し寄せており、ここ数年は中学校での性差の少ない制服の採用が活発化している。従来の詰め襟とセーラー服から、男女の違いが出にくいブレザータイプへの変更に加えて、自分のスタイルに合わせてスラックスやスカートが選べる。つまり、性別でアイテムを絞るのではなく、どの制服でも着用できるように選択肢を広げることで、学校生活を送る上での不安を解消することが目的になる。
また、地球規模で進む温室効果ガスの排出や生態系の崩壊など環境問題が深刻化するこんにちでは、企業のみならず個人においてもサステナビリティな取り組みが求められるようになっている。そうした中でペットボトルを再生した原料を使った制服、石油から作ったポリエステルではなく、植物や動物由来の繊維を使った制服、化学薬品を使わずに栽培されたオーガニックコットンやエコフレンドリー染色なども選択できるようになっているほか、着ることで涼しさや暖かさなどを感じられる機能が付いた制服といった、CO2排出量や廃棄の削減につながるような素材や機能を持つ環境配慮型の商品開発が進んでいる。
家庭の負担を減らすリユースやエリア標準服
併せて、家庭の経済格差や制服代の高騰などを背景に、商品の寿命を延ばしたり、繰り返し着用したりすることが不可避になり、卒業や成長に伴って着られなくなった学生服を再利用や再販売するリユース&リサイクルのニーズも高まっている。こうした状況を踏まえ、制服メーカーの中には従来行ってきたサイズ直しや修繕だけでなく、自主的に学校や制服販売店などに学生服の回収ボックスを設置し、流通・販売を支援する動きも起きている。
さらには家庭の経済的な負担を減らそうと、自治体単位で制服の仕様を統一化(エリア標準服)する動きも各地で見られるようになっている。スケールメリットを生かして価格アップを抑えるとともに、自治体内で転校した際に学生服を買い替える必要がない、譲り渡しによる再利用を加速できるといったメリットがあるからだ。それ以外にも、性別によって制服が制限されない選択制の推進や、地域への誇りや愛着、公平性の向上につながるといった狙いもある。
2020年より導入した福岡市と北九州市をきっかけに検討する自治体が増えており、例えば鹿児島県南さつま市の市立中学校と義務教育学校も、今年度からブレザー型のエリア標準服を導入した。そこではリボン・ネクタイの柄やシャツの色は各校が決められるようになっており、独自性を出せるように配慮している。また、岡山県井原市も来年度から市内の中学校で共通デザインの制服を取り入れる予定となっている。
学生服からマインドセットを図る
多様な個性を尊重する意識の高まりで、生徒が主体になって性別にとらわれない制服を「第3の制服」として考案する動きが広がっている。栃木県にある高校では、生徒会長の選挙公約として第3の制服の導入が主張され、生徒や教員、制服業者などが協力して検討。その結果、既存の学ランやセーラージャケットに加え、性別を問わず選択できるジャケットが導入された。ジャケットは、体形に合わせ直線型と曲線型の2タイプが用意されており、男子のスカート着用も認められている。
学校教育の使命は、将来、社会生活を営む上で必要とされる知識・技能や態度を育成することにある。それ故、学校文化の一つを形成する学生服というアイテム自体にも、このような多様性の理解しかり、こんにちの社会を反映した教育課題に応える仕様や表現を用いることが求められているのだ。
したがって、これからの予測困難な時代を生き抜く力を育てる学習者主体の教育への転換や先端テクノロジーの活用など、新しい時代の学びが提唱されている学校現場では、制服のあり方の見直しやモデルチェンジをきっかけに、姿かたちからマインドセットを図り、教職員を含めて意識改革を促していこうという意図が込められている。
着心地や快適性を追求した新素材を開発
一方、少子化による教育熱の高まりから、私立学校を中心に個性化・差別化が必要になり、学校ごとの要望に応えたデザインやディテールなど、きめ細やかなサービスを提供することも欠かせなくなっている。このため、個々の学校のアイデンティティーを表現するデザインやブランディングの提案とともに、着心地や快適性などの機能性を追求したオリジナル素材による高付加価値商品も、各制服メーカーが切磋琢磨する中で次々と生み出されるようになっている。
動きやすいストレッチ素材や吸汗速乾素材、家庭で手入れがしやすいノーアイロンやウォッシャブル、撥水、防臭、抗菌加工などは今や当たり前となり、制服メーカーでは新たな訴求ポイントとなる、さらなる新素材の開発が進められているところだ。また、年々猛暑が厳しくなり、紫外線カットや通気性などの機能強化に加え、よりカジュアルな装いで快適に過ごすことができるポロシャツやショートパンツなどが、新しいアイテムとして取り入れられるようになっている。
有名ファッションブランドとコラボレーションしたブランド学生服は、一般の制服よりも素材や縫製技術、色調にこだわり、クラシカルで上品なデザインが主流だ。しかし現在は、これらに加えてネクタイやリボンと合わせたTPOごとの着こなし方の提案が大事になっている。それ故、ブラウスやセーター、ベスト、ポロシャツなどの着せ替えアイテム、コートやバッグといった制服回りの商品はもちろんのこと、ブレザーの上から羽織れるウインドブレーカーやスタジアムジャンパーといった、スポーツアウターも取りそろえるようになっている。
スポーティー化する「体操服」の進化
こうしたデザインの進化は、学校の体育で着用する「体操服」にも波及。今や多くの制服メーカーがスポーツウエアメーカーとのライセンスブランドを展開し、スポーツ競技者が着用するような機能的で見た目もカッコいい体操服を提案するようになっている。加えて、学生服メーカー自体も、これまで制服で培った技術やノウハウをスポーツウエアに生かし、自社ブランドを立ち上げるところも多くなっている。
その要因の一つには、コロナ禍を契機に学校の着用ルールが変わり、登下校中や授業中、課外活動も含めて体操服の着用機会が広がったことがある。それだけに、見た目がだらしなく見えず、生徒たちに身なりを気にかけてもらうためにもデザイン性が重視されるようになった。併せて、着心地や快適性なども追求されるようになっており、防風性やストレッチ性、軽量、吸汗性、透け防止など多様な機能が盛り込まれるようになっている。
デザイン面の傾向としては、こちらもジェンターレスを意識し、かつ多様な体型やスタイルに対応できるようにするため、男女問わず着用できるユニセックスなデザインが増えているのが特徴だ。また、シンプルで洗練されたデザインが好まれる中でも、アクセントとして差し色を取り入れ、差別化を図る工夫なども見られている。
さらには、ウインドブレーカーやパーカー、スエットなどを加えたセットアップ提案も増加。制服と合わせた場合の着こなしも意識されるようになっており、制服も含めたスポーティー化がトレンドになっている。