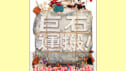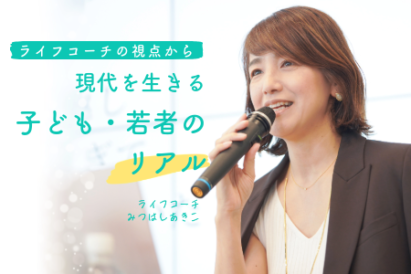絵で見る 日本の図書館の歴史
16面記事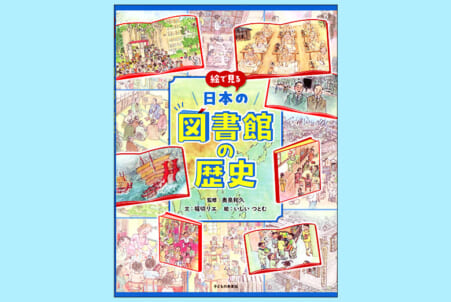
奥泉和久 監修 堀切リエ 文 いしいつとむ 絵
町や学校などにある図書館は、いつ、誰が、何のために造ったのだろうか。
本書は現在の日本の図書館ができるまでの歴史や背景となる思想などを絵や写真などを交えながらまとめたものだ。
多数の書物を長期間保存するため正倉院が建てられたことや東大寺の写経所、鎌倉時代の金沢文庫、室町時代の足利学校の付属文庫など各時代の取り組みを紹介。明治から大正にかけては、図書館の父と呼ばれる佐野友三郎の活動や文部省による図書館司書の養成機関の設置、東京市立日比谷図書館の建設などが描かれる。
巻頭には年表を掲載しており、主な流れを把握できる。図書館学五つの法則を含め、図書館について広く学びたい人に役立つ内容だ。(小学校中学年から)
(3300円 子どもの未来社)
(Tel03・3830・0027)