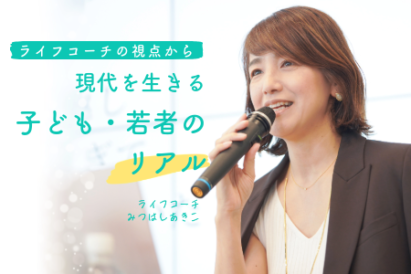日常ではできない体験を通して”生きる力”を育む 農林水産省が推進する「農泊」の取り組み
12面記事
茶摘み体験の様子
観光から学びの旅へと変わる教育旅行。中でも、自然や地域の人々と触れ合い、食の大切さ、社会とのつながりを体験できるのが「農泊」だ。そこで、コロナ禍を経て再び注目を集める「農泊」の取り組みについて、農林水産省の東崇史農泊推進室長に聞いた。

東 崇史 農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交流課 農泊推進室長
自然・文化体験や交流を通して
―感覚を養うということですが、具体的に教えていただけますか。
「農泊」とは、農山漁村に宿泊して、その地域の自然や文化を体験したり地域の人たちと交流したりする農山漁村滞在型旅行のことです。日本ならではの伝統的な仕事や生活にじかに触れてもらい、その土地の魅力をじっくり味わってもらうことを目指しています。こうした背景には、農山漁村の多くは人口減少と高齢化が同時に進行しており、地域の保全やコミュニティの維持が課題になっていることがあります。そうした中で、古民家に宿泊し、ジビエ、棚田などの地域資源を活用したさまざまなコンテンツを提供することで、長時間滞在していただき、持続的な収益を確保して雇用を生み出すとともに、移住・定住も見据えた関係人口創出の入り口にしたいというねらいがあります。
自然学校として長期宿泊を行う自治体も
―学校が農泊を利用する場合は、修学旅行が多い?
学校の利用は修学旅行に限ったわけではなく、特に都市部の中学校などでは自然教室や林間学校などの行事で、農林作業やホームステイ型の民泊体験を行うところもあります。農山漁村の民家などに宿泊して一緒に郷土料理を作ったり、幅広い年齢層の方々と交流したりすることは日常ではできない貴重な体験であり、これらを通して生きる力や異文化への理解が育まれる意義があると考えています。
例えば東京のとある自治体の小中学校は、セカンドスクールとして1週間ほど滞在していると聞いています。これは自然豊かな農山漁村に長期宿泊を行う教育活動であり、普段の学校生活(ファーストスクール)では体験できないような学習活動を授業の一部として行っているのが特徴です。
受け入れ側の減少やモチベーションが課題
―コロナ禍を経て再び注目されている農泊の現在の課題は?
やはり、コロナ禍で期間が空いて高齢化が一層進んでしまった影響は大きく、継続が不可能になったり、受け入れを止めてしまったりする事例が増えていることが課題になっています。とりわけ、学校が利用する場合は一集落に何件も民泊できる場所を用意する必要があるため、これまで通りに受け入れることが難しくなっている現状があります。したがって、一地域だけでなく、複数地域が広域で連携して多くの生徒さんを受け入れるケースや、日中の体験活動だけ受け入れて、夜は地域にある旅館・ホテルに宿泊するケースなど、農山漁村滞在型旅行としてのさまざまなパターンを構築していく必要もあると思っています。
また、継続していく上では、現状宿泊単価が安価であることも課題の一つになっています。これについては単に値段を上げるのではなく、「行ってよかった」と思ってもらえる体験内容に磨き上げていくことが大事だと。つまり、農泊そのものの付加価値を高め、適正な値付けをすることで事業を継続していきたいと考えており、そのために農林水産省では地域向けの補助金制度も設けて支援しています。
―学校関係者に向けてメッセージを
自然環境が豊かな農山漁村だからこそできる体験がたくさんあります。多くの学校の子どもたちに、そんな日常ではできない体験をしてください。今後も関係者と協力して取り組みを進めていきたいと考えています。