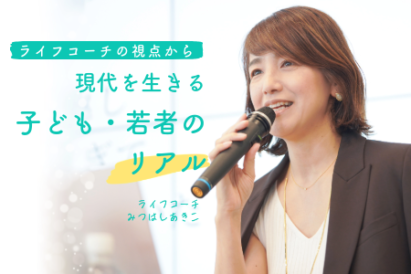行程に分散化のひと工夫を加えて得られたこととは
11面記事
沖縄県
沖縄県を訪れる修学旅行の入込数は、令和5年度で1933校33万9152名となり、校数、人数ともに順調に増加し、回復傾向にある。一方で、修学旅行の実施時期は、4月~6月、10~12月に集中しており、繁忙期には観光施設、体験施設や生徒の乗降場所における混雑のほか、貸し切りバスの予約が困難となる状況にある。そのため沖縄県では、国の「重点支援地方交付金」を活用した令和6年度修学旅行需要分散化促進支援事業を設け、41校約6000名が活用した。本事業は、沖縄県を修学旅行で訪れる中学校・⾼等学校を対象に、移動手段の需要や特定の場所における訪問・集合・離散の場所、時間帯の集中を避けるための「分散化」を考慮した行程へ変更することに加え、SDGsまたは探究学習プログラムを追加することを主な条件に、一人あたり1万円を上限とし、追加する体験プログラムの実費相当額を支援するというもの。行程の変更により、訪問先での混雑や交通渋滞を回避することで活動時間のロスを防ぐことができたほか、体験プログラムの追加により、参加する生徒にとっては、沖縄の⽂化や⾃然をより深く理解できる契機となり、地域経済の活性化にもつながった。

実施校の声(1)(移動手段の分散)
連泊の中日にタクシー研修を取り入れ、貸し切りバス利用をカットした。タクシー研修を取り入れたことで余った時間には、ホテル前のビーチでの散策や班別での体験プログラムを加え、時間的、体調面でも無理のない行程でよかった。
実施校の声(2)(訪問時間帯の分散)
元々は全クラス一斉に朝の首里城公園へ訪問する予定としていたが、別の場所との入替制としてクラス別に訪問時間帯の分散を図った。先に首里城を訪問した班が朝の混雑に巻き込まれ、これが全クラス一斉に訪問していたらと思うとぞっとした。分散して大変良かった。
実施校の声(3)(体験場所の分散)
石垣島以外(周辺離島)での実施を増やしたことで、引率の手は分散してしまったが、生徒の体験の選択肢の幅が広がったことは非常に良かった。また、今回は天候等によるプログラム中止はなく、すべて予定通りに進めることができたが、こうした体験場所の分散により、中止等のリスクを最小限にとどめることができるのではと感じた。
事業を振り返ってみて
本事業を活用した実施校へアンケート調査を行ったところ、約97%の学校が「活用して良かった」と回答した。物価高騰により旅行費用が厳しい中で、本事業を活用することで、より学びの深い修学旅行になった事が今回の成果であった。ウェブページには実際のより詳細な行程や実施校の声などが実体験として掲載されている。今後の修学旅行行程の参考に目を通してほしい。
問い合わせ=一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 教育旅行チーム 電話098・859・6129
おきなわ修学旅行ナビホームページ https://education.okinawastory.jp/