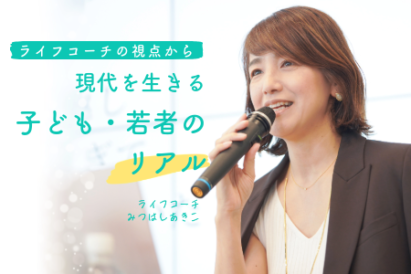鼎談 「これからの修学旅行」を考える
9面記事
左から竹内氏、和久井氏、岩瀬氏
コロナ禍を経て復活した修学旅行は「学びの集大成」を図る機会として期待されている。しかし、物価高や人手不足に伴う旅費の高騰、インバウンドによるオーバーツーリズムに直面し、持続することさえ困難な状況を迎えつつある。そこで、関係する識者を招き、これらの課題を踏まえた修学旅行のあり方について語ってもらった。
出席者
和久井 伸彦 文部科学省 初等中等教育局教育課程課 教科調査官(特別活動)
岩瀬 正司 全国修学旅行研究協会・理事長
竹内 秀一 日本修学旅行協会・理事長
コロナ禍で再認識された修学旅行の意義
―コロナ禍とアフターコロナに向かう現在、修学旅行はどう変わりましたか?
岩瀬 コロナ禍で見えてきたものが三つ。一つは、文部科学省から再三にわたり、中止でなく工夫して実施を、という通知が出されたことで、修学旅行は学校教育の中で重要な位置を占めていると改めて認識した。二つ目は、そういう意味でも日本人の大半が経験している修学旅行は、日本文化そのものだと再認識したこと。三つ目は、学校単独では実施できないことに、学校が気付いたことです。運動会や文化祭などの行事はすべて学校内で完結できるが、修学旅行は旅行会社や宿泊先、交通機関も含めていろいろな人の支えで成り立っており、経済的な側面も有している。つまり、修学旅行とは、重要な教育活動であり、日本文化であり、経済的な側面を持つ、この三つの視点がコロナ禍で明らかになったと認識しています。
そして、現在はどう変わったかというと、旅費の高騰と人手不足が進んで今までのような当たり前の修学旅行を実施することが困難になっている状況です。
竹内 高校でも、感染リスクが高いのに修学旅行を行う必要があるのかといった議論が起きた時期がありました。その中で、学校としては改めて修学旅行の意義を問い直す機会になったとともに、コロナ禍の中で新しい学習指導要領が施行され、学びに重点を置いた修学旅行にする考えが高まったと感じています。ただし、現在は旅費が上がって、今までと同じ行程で実施することが難しい状況になりつつあるほか、インバウンドの増加により、貸し切りバスやタクシーを押さえることさえできない。旅行会社なども人手不足によって、入札そのものを辞退する動きも出てきているなど、修学旅行を取り巻く環境が非常に厳しくなっています。
京都・奈良集中を変えるには
―旅費の高騰は、東京都葛飾区が区立の小中学校を対象に修学旅行や林間学校の費用を全額無償化すると決めたように、公的支援が解決策の一つになると思いますが、オーバーツーリズムに対する学校側としてできる対策は?
岩瀬 訪問先や時間を変えればある程度は緩和できるかもしれませんが、中学校の修学旅行では一部に安・近・短の1泊2日にする流れが起きています。現に東海地方のある地域では、市全体でそれを決めて実行しています。教員の負担軽減という安易さではなく、修学旅行の本質・目標を徹底検討の上での実施が望まれます。
竹内 これだけ京都・奈良が混雑しているのに相変わらず修学旅行先として人気なのは、教員が多忙で新しい誘致先を検討する時間がないことも影響しており、安全安心確保の点からも離れられない状況が続いているといえます。
和久井 行先も大事ですが、やはり何のために行くのか、どんな資質・能力を身に付けさせたいのかを考えて場所や時期を設定することが大事と考えます。文部科学省としても、実施時期を柔軟に検討してもらうよう通知を出したり、教育的意義の観点から修学旅行の機会に活用いただけると考える内容例を紹介したりしています。国も含め、さまざまな機関が協力して解決策を探っていければと考えています
学習指導要領での立ち位置
―そのような過渡期にある修学旅行ですが、学習指導要領での立ち位置とは?
和久井 修学旅行は、学習指導要領における特別活動の中の学校行事の一つに位置付けられています。内容としては、日常と異なる環境の中で自然や文化に親しむこと、よりよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳を学ぶことなどが示されています。特に小学校では、自然体験の減少ということから自然の中における集団宿泊活動を行うことが望まれています。また、特別活動において育成すべき資質・能力の重要な視点として人間関係形成、社会参画、自己実現が示されており、修学旅行を行う場合も、この視点を用いて子供たちの資質・能力を育成していきます。
岩瀬 私どもの協会では修学旅行を物見遊山的な観光旅行ではなく、「学びの集大成を図る機会」にすることを、この10数年間ずっと訴えてきました。修学旅行は教育活動の一環であり、特別活動としてのさまざまな目標に沿った資質・能力を身に付ける必要がある。同時に「総合的な学習の時間」を含む教科学習のまとめや実践・体験の場である。さらには道徳的な実践力を高める場でもあり、学校教育のすべての分野を実践しやすいのが修学旅行の機会であると思っています。
竹内 高校では、現行の学習指導要領で「総合的な探究の時間」が新設され、修学旅行を探究的な学習の機会にしたいというニーズが高まっています。なぜなら、以前とは違って修学旅行での体験活動を本学習に結び付けてもいいことになったからです。
現地での交流を重要視
―特別活動の一環であることを踏まえ、育成したい資質・能力とは?
岩瀬 今、教室の掃除や給食の配膳を黙々とこなす子供たちの姿を見て、国際的に日本の特別活動の評価が高まっています。修学旅行も、そうした特別活動の一環である意義をもっと全面的に打ち出していく必要があるのでは。
竹内 修学旅行で重要視されているのは、現地で関わる人との交流です。対話や議論、自分とは違った考え方に触れることで視野を広げ、多角的に物事を考える力を身に付ける。その中で、社会生活における人間関係形成能力を同時に築いてほしいと考えています。
和久井 集団宿泊的行事においては、共に過ごす時間も長く、友達との関わり合いを深め、共に協力し合うなどのよりよい人間関係を形成しようとする力を育成していきます。また、より充実した活動にするため、意見を出し合い、合意形成しながら課題を解決する力や、目標に向けて粘り強く実践する力などを育成することも重要です。
受け入れる側の課題
―子どもたちを受け入れる側の課題はありますか?
岩瀬 ホテルや旅館では、食物アレルギーへの対応が大きな負担になっています。アレルギー原因物質を除いた共通メニューを提供するところもありますが、生徒も提供する施設にとっても課題は大きいです。学校や旅行会社も含め、修学旅行は実施する学校・生徒、受け入れる旅行関連事業者、そして社会全体の「三方よし」で実現していかないと、この先厳しくなるのではないかと危惧しています。
竹内 自治体も、旅費の高騰に対応して旅行会社や学校向けに補助金を出すようになっています。しかし、多くは単年度予算であり、修学旅行のスケジュールは1年半から2年前に決まることから、その時点で使えるかどうか見通しが立たず、利用しにくい側面もあります。
―最後に、学校関係者に向けてメッセージを。
岩瀬 今年は昭和100年、戦後80年。修学旅行が行えるのは、日本が平和だからこそ。その思いがある中で学校の先生方に伝えたいのは、修学旅行を楽しんで欲しいということです。先生方が楽しくなければ、生徒も楽しめませんから。
竹内 やはり私は、修学旅行というのは子どもにとってはかけがえのない学びの機会であると伝えたい。だからこそ、関係する機関には将来の日本を担う人材を育てることを意気に感じ、積極的に関わってほしいと切に願っています。
和久井 スマートフォンやタブレット等のICTの機器の普及により実感の伴った体験が不足する中で、自然や文化に直接触れることができる修学旅行は、子どもたちの成長に重要な役割を担うと思っています。修学旅行を通して育てたい資質・能力を明確にし、子どもたちにとって一生忘れられない思い出になったり、これからの生活の支えになったりする有意義な活動にしていってほしいですね。