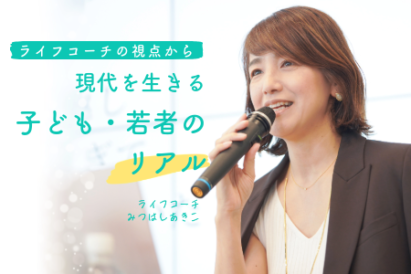アカデミックハラスメントとは? 深刻化する背景や求められる対策
トレンド
個人の尊厳や人格を不当に傷つける行為であるハラスメントは、個人の能力発揮を妨げるものであり、人権に関わる重大な社会問題の一つです。教育機関においても発生する可能性があります。
この記事では、主に大学・大学院などの高等教育機関において発生する「アカデミックハラスメント」の具体例や対処法、防止対策などについて詳しく解説します。
アカデミックハラスメントとは
アカデミックハラスメント(以下「アカハラ」)とは、大学や大学院などの教育・研究機関で起きる、「嫌がらせ」や「いじめ」を指します。
例えば、大学等の学内で教職員が教育・研究上または職場での権力を利用して、学生・大学院生等の教育指導や研究活動に関係する妨害を行ったり、不利益を与えたりする行為が挙げられます。
出典:厚生労働省『第4章 大学組織・学生等との対応の理解』
ほかのハラスメントとの違い
現代では、さまざまなハラスメントが存在し、職場や教育現場などの環境、ハラスメントを受ける対象ごとにおおまかに区別される名称があります。
▽ハラスメントの種類
・アカデミックハラスメント(アカハラ):大学等の学内で教員や職員が権力を利用して学生等に行う嫌がらせ
・パワーハラスメント(パワハラ):職務権限(職務上の地位や立場)を使った嫌がらせ
・セクシャルハラスメント(セクハラ):意に反する不快な性的言動
アカハラやセクハラは、上下関係を利用した嫌がらせとして、パワハラに分類される場合があります。
出典:厚生労働省『第4章 大学組織・学生等との対応の理解』
アカハラが深刻化する理由や背景
部外者や第三者がアカハラの有無を判断・調査することが容易でないことに加え、法制度化も不完全なため、厳罰化が困難な現状があります。
教職員は、成績認定権といった立場上の権力のほか、知的能力や社会的威信の面で学生に対して明らかに強い立場にあります。アカハラの被害者は、信頼する教職員に裏切られたショックがあること、また、卒業、資格・学位取得、研究キャリアなどが妨害される恐れがあるといった懸念から被害を公にできないといった点も、アカハラが深刻化する要因だと考えられます。
さらに、教職員が管理・保有している資料や書籍・施設・研究対象者・フィールドが存在していることや、研究室での共同研究を行う必要があるなど、被害者と加害者の接触をなくすことが難しいことも今後改善すべき課題とされています。
出典:厚生労働省『第4章 大学組織・学生等との対応の理解』/文部科学省『資料2 キャンパス・セクシュアル・ハラスメントの実態と課題』
アカハラの具体例
アカハラといっても被害の内容はさまざまです。
▽アカハラの例
・暴言・暴力・差別的発言
・ソーシャルメディア上やメールでの誹謗中傷
・本来受けられるべき適切な研究指導を受けられない
・プライバシーの侵害
・研究やキャリアの妨害
・雑用や論文制作手伝いなどの強要
・研究成果・アイデアなどの盗用
・教育指導や研究の場での性的嫌がらせ(セクハラ) など
具体的には、不当な理由で推薦状や実績証明書などの記入を拒否され、就職活動において不利な扱いを受けたり、研究室内やグループ内で悪い評価が共有されたり、さまざまな嫌がらせが発生しています。
出典:厚生労働省『第4章 大学組織・学生等との対応の理解』『アカデミック・ハラスメントの構造』/文部科学省『資料2 キャンパス・セクシュアル・ハラスメントの実態と課題』
ハラスメントが起こったときの対処法
学内でハラスメントが起こったときは、学内や公的機関などの相談窓口で相談することが重要です。専門相談員が内容を整理し、問題解決や被害回避方法を検討します。専門の相談窓口では、被害者だけでなく、ハラスメントに気づいた被害者以外の知人や友人が相談することも可能です。最近では、自分の行動が相手にハラスメントと受け取られてしまったケースに関する相談が寄せられることもあります。
相談員は相談を受けたあと、関係する部局等に依頼を行い、関係の改善や必要な措置が取られるように調整を働きかける役割があります。
また、調整で解決しない問題や、相談者が望む場合には、申立てを行い調査委員会で調査・審議を行う必要があります。審議後は、組織のトップへ報告し、懲戒や警告、学生への特別措置等の対応を決定するという流れです。公平さを保つために、専門知識のある調査委員会も交えて対処するのが有効だと考えられます。
出典:文部科学省『「大学教育改革の実態把握及び分析等に関する調査研究」~大学におけるハラスメント対応の現状と課題に関する調査研究~』
アカハラの防止対策と課題
アカハラが深刻化するのを回避するために、防止対策を実施している学校もあります。
▽アカハラの防止対策
・ガイドラインの策定
・相談員の配置(専門相談員)と相談室の設置
・教職員研修の実施
・ハラスメント相談窓口の存在の周知
・学生サポーターから学内ハラスメント事例の情報収集 など
これらの対策は、教育機関ごとにばらつきがあるほか、専門相談室を持つ大学は限られているのが現状です。今後の課題として、対策にかかる費用の問題や相談員の業務不負担軽減などが挙げられています。
出典:文部科学省『資料2 キャンパス・セクシュアル・ハラスメントの実態と課題』『「大学教育改革の実態把握及び分析等に関する調査研究」~大学におけるハラスメント対応の現状と課題に関する調査研究~』
アカデミックハラスメント防止に欠かせない教育機関の対応
教育機関では、閉鎖的な人間関係からハラスメントにつながることがあります。教職員と学生の両者を守るためには、教育機関側が対策を講じ、迅速に対応することが重要です。
各教育機関がアカハラに対する認知を深め、発生防止の施策に積極的に取り組むことが求められます。専用相談窓口や専門知識を持つ相談員の設置、アカハラが発生した際の適切な措置などを充実させることで、学生・大学院生が安心して学べる環境を整えることに期待が高まっています。