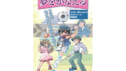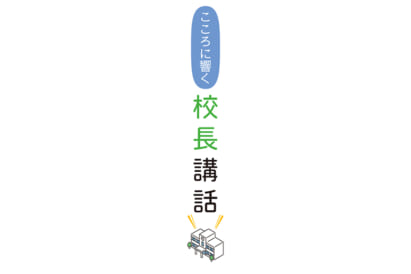実社会で進むサステナブル活動から学ぶ~「自分ごと」として捉え、日常で実践できる力を育成する~
12面記事
持続可能な社会の実現には産業と環境のバランスが重要になる
誰一人取り残さない、持続可能な社会の実現に向けて、未来を担う子どもたちには今から実社会・実生活の中から課題を見つけ、自己の行動へとつなげる「環境・エネルギー教育」が欠かせなくなっている。ここでは、そのための生きた教材として期待されている企業のサステナブルな活動を取り上げる。
豊かな生活の代償としての環境問題
大量生産・大量消費による産業活動の発展は、世界の多くの人々の暮らしを豊かに、便利にした。しかし、その一方で二酸化炭素が大量に排出された結果、地球は温暖化が進み、豪雨や干ばつなどの自然災害が頻発するようになった。加えて、工業・生活排水やプラスチックごみによる海洋汚染が広がり、海で生きる生物たちの生態系を脅かす事態となっている。
こうした多くの環境問題は、経済的・社会的に、より脆弱な国や地域・人に対し、より深刻な影響を与えるようになっている。同じく、気候変動や生物多様性損失等の問題も、その原因を担ってきた過去・現在の世代よりも、将来の世代により深刻な影響を与えることは間違いない。
それだけに、21世紀を担う子どもたちには環境保護と生活利便性の両立について考え、「自分ごと」として捉える力を育むための「環境・エネルギー教育」がより一層重要性を増している。とりわけ、エネルギー源や食料を海外からの輸入に依存しているわが国では、常に安定供給と環境負荷の低減が、両輪のように付いて回る課題になっている。
「自分ごと」として考えを深めるために
だが、このような私たちが生きる上で必要な実社会の経済活動と結びついた環境問題をテーマに学びを進めるには、学校の中だけでは教材や指導に限界があり、不十分だ。そのため、今や持続可能な社会への貢献が不可避となっている企業のサステナブルな活動から学び、「自分ごと」として考えを深め、「日常で実践できること」へとつなげていくことが期待されている。
なぜなら、「今後長期間にわたって地球環境を壊すことなく、資源も使い過ぎず、良好な経済活動を維持し続けていくためにはどうすればいいのか?」といった二律背反する問いについて、実社会ではどのようなことが行われているかを知ることが、自分の行動に置き換えるためのヒントや生きた教材になるからだ。
未来社会を切り開く力を育成する
もう一つ、現行の学習指導要領では、小中高等学校を通じて「探究的な学び」への取り組みが重視されている。AIやIoTといった科学技術が急速に進化し、将来予測が困難な時代を迎える中で、これからの子どもたちには自ら課題を見つけ、解決していく力を身に付けることが求められているからだ。そこでは、他教科の見方・考え方を結びつけて総合的に活用することに加え、実社会・実生活の課題を探究して自己の生き方を問い続けるといった、一歩進んだ展開が望まれている。
こうした意図からも、複雑な要素がさまざまに絡む環境・エネルギー問題について学ぶことは、仮説検証やデータ分析、論理的思考などのスキルを磨く必要があるほか、情報を鵜呑みにせず、批判的に考え、自分の意見を形成する力が養える。しかも、議論したり、解決策を提案したりすることで、自分の考えを分かりやすく伝え、相手の意見を聞き、理解するコミュニケーション能力も育むことができる。
さらに、環境問題は国境を越えて解決する必要があることから、探究を通して異なる文化や価値観を理解し、国際理解を深めることも可能になる。そして、こうした学びを進める上においては、実際に取り組んでいる企業のサステナビリティー活動から得る視点は極めて大きいといえる。
企業がサステナビリティーに取り組む理由
では、なぜ現在、企業においてはサステナブル対応が欠かせない取り組みになっているのか。その一つの理由が、社会的な責任といえる。近年、消費者は環境負荷や社会貢献に配慮した企業の製品やサービスを好む傾向が強まっており、購買行動を左右するようになっている。その中で、サステナビリティーへの取り組みを重視することは、企業イメージや顧客満足度の向上などの効果が期待できるからだ。
2つ目は経済的なメリット。これからの時代に不可欠な省エネ技術や環境に配慮した製品の開発は、新たなビジネスチャンスを生み出す可能性がある。また、気候変動や資源の枯渇が企業の業績を悪化させることが想定される中、サステナビリティーに取り組むことで、こうしたリスクを低減し、長期的な安定成長につなげることができる。
3つ目は、社員のモチベーション向上につながることだ。自分の仕事が社会に貢献していると実感すれば、より高いパフォーマンスを発揮できるようになり、企業のビジョンや姿勢が明確になることで社員の帰属意識も高まるといった効果もある。
さらに、近年では投資家も財務状況の判断だけでなく、環境問題への取り組み、地域社会への貢献、適切な労働環境ができているかを重視して投資を行うようになっている。
つまり、企業にとってサステナビリティーへの取り組みは、社会信用の獲得というカテゴリーにとどまらず、競争優位性を獲得するための重要な要素となっているのである。
持続可能な社会について考えるきっかけに
その中で、例えば企業の環境負荷への取り組みとしては、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用、環境に優しい物流システムの構築、オフセット(排出量削減への投資)、カーボンニュートラルの達成など温室効果ガス排出量の削減が挙げられる。
また、資源の有効活用では、リサイクル・リユースの推進や廃棄物削減、省資源型製品の開発・販売、グリーン購入(環境に配慮した商品・サービスの調達)、環境汚染の防止では、化学物質の使用削減や排水・排出物の処理、環境に配慮した製品・サービスの開発・販売、生物多様性の保全では、森林伐採の防止や生態系への配慮、生物多様性保全活動への参加、環境経営の推進では、環境マネジメントシステム(EMS)の導入や環境教育・啓発、地域社会への貢献活動、社員全体の環境意識の向上、環境報告書の発行を進めるなどが代表的な例となる。
これらの企業の取り組みは、子どもたちが実感として持続可能な社会について考える入口になり、それを自身の活動や課題研究へと発展させていく手がかりとなる。
また、企業においても、教育現場を支援することは社会貢献としてのメッセージを発信しやすいことから、出前授業や体験プログラム・教材などを提供する動きも広がっているのだ。