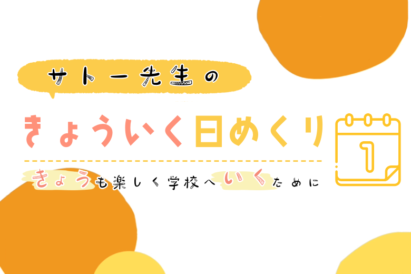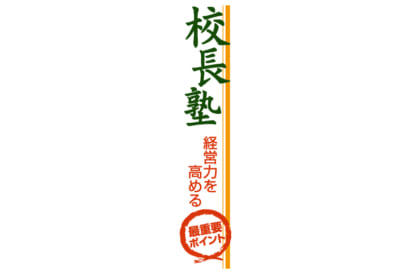水害リスクが高まる学校施設の浸水対策を
11面記事
浸水対策の取り組みが進んでいない
学校施設の防災対策については、東日本大震災を教訓に、構造体の耐震化や吊り天井等の非構造部材の耐震対策をはじめ、津波対策や、災害時は避難所となる学校施設の防災機能の強化が進められてきている。
一方、水害対策については2018年7月豪雨や翌年の台風19号、2020年7月豪雨等により、学校施設でも大きな被害が発生したことを踏まえ、文科省では対策の推進を図っているが、2020年10月時点の調査によると、公立学校施設での浸水対策等の取り組みは進んでいない状況にある。とりわけ、「浸水想定区域・土砂災害警戒区域」に立地する学校が3割ある中で、施設内への浸水対策や受変電設備の浸水対策などハード面の対策を実施している学校は約15%しかないことが大きな課題になっている。
学校施設の水害対策における手引を公表
こうした中、文科省が今年の5月に発表したのが「水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進のための手引」になる。これは頻発化・激甚化する豪雨等に対し学校施設の水害対策の強化を図るべく、文科省の協力者会議が検討した結果をまとめたものだ。
学校施設の水害対策の基本的な考え方としては、緊急時の児童生徒等の安全確保とともに、学校教育機能が長期に中断しないようにする対策が求められる。これまでの浸水被害では、地震災害と比べても休校期間が長期化する傾向があるからにほかならない。
また、公立学校の約9割が避難所に指定されている学校施設は、水害が発生した際も避難所としての機能を継続することが求められると同時に、洪水等の危険が迫った状況でも、住民等の生命の安全を確保する施設として機能しなければならない。加えて、気候変動の影響による降雨量の増加に対応し、地域全体で治水対策に取り組むことが必要になっていることから、雨水貯留施設の整備などの役割を担う必要も生まれているとした。
関係部局と連携した検討がカギ
その上で、学校設置者における水害リスクを踏まえた浸水対策では、専門的な知見をもつ関係部局と連携して検討する体制を構築することがより重要になると指摘。例えばハザード情報については、年超過確率別の浸水想定図と学校位置の重ね合わせをするなど、学校ごとに想定される浸水リスクを整理するとともに、想定最大規模の降雨による浸水範囲や浸水深だけでなく、より発生頻度の高い浸水想定にも着目して対策を検討することを挙げている。
すなわち、施設の脆弱性の確認後に、学校周辺の浸水深と頻度からハード・ソフト両面の対策を講じる範囲を検討することだ。例に挙げると、
(1) 想定される浸水深は大きいが発生頻度が低い場合は、事前避難等のソフト面の対策を前提とし、ハード面も検討する
(2) 想定される浸水深は大きくないが発生頻度が高い場合は、ハード面の対策を基本に検討する
―などである。また、学校ごとの実情に合わせた検討でいえば、水害リスクを踏まえて長寿命化改修計画を作成する、想定浸水深が大きい学校施設から優先的に整備していくことが考えられる。
止水板やかさ上げなどで電源を確保することが重要
こうした中で、緊急時に児童生徒等の安全を確保するための対策のポイントとしては、危機管理マニュアルや気象情報を的確に活用して、危険が予測される場合は学校に来させない、早めに下校させるといったソフト面での対策を前提に、学校設置者と学校が連携してハード面の対策も検討することが重要とした。
具体的には、校舎上階の避難スペースや備蓄品の確保、新築・増築時のピロティによる高床化や敷地のかさ上げ、受変電設備のかさ上げ、校内への流水を防ぐ止水板の設置、校舎への土砂被害を防ぐ壁体の整備、要配慮者の垂直避難のためのバリアフリー化などになる。
学校教育活動の早期再開のための施設の被害軽減・早期復旧対策としては、何より受変電設備等が浸水から守られ、普通教室・職員室等が利用可能な状態にすることがポイントになる。そのほか、床下換気口への浸水対策(止水板等)、逆流防止弁の導入、コンセント位置の修正、内装材の工夫、オーバーフロー管の設置等が有効とした。
本手引きでは、これらの対策をした場合の費用と、対策をしなかった場合の被害額も並べて掲載している。なお、受変電設備が浸水した過去の例では、応急復旧まで2カ月強、架台設置まで8カ月を要した。今年の夏も線状降水帯による豪雨が全国の広い地域で発生しており、今後も増加していくことが確実視されている中で、学校施設の浸水対策にも本腰を入れていく必要がある。