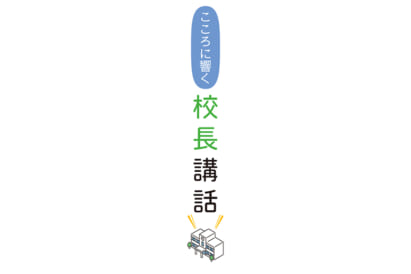jicpa会計教育シンポジウム2025 探究学習を深める会計リテラシーを開催~社会科での実践を踏まえて~
14面記事
パネルディスカッション〈探究パート〉の様子。左から鶴田氏、加藤氏、辻氏
日本公認会計士協会は3月29日、東京都千代田区のアルカディア市ヶ谷私学会館で「jicpa会計教育シンポジウム2025」(協力=日本教育新聞社)を開催した。テーマは「探究学習を深める会計リテラシー~社会科での実践を踏まえて~」と設定。中学校社会科や高等学校公民科での「会計」に関わる授業実践の知見を踏まえつつ、総合的な学習(探究)の時間における「会計リテラシー」の活用方法を探った。基調講演に続き、各地の教員や有識者による実践を踏まえた2つのパネルディスカッションが行われ、中学校・高等学校の教員や幅広い教育関係者約50名が参加した。
会長挨拶
「生きる力」の育成に貢献する会計リテラシー
茂木 哲也 日本公認会計士協会 会長

「会計リテラシー」はさまざまな場面、ライフステージにおいて、全ての人々に必要かつ有用なものです。現行の中学校社会科・高等学校公民科の学習指導要領解説において、会計情報の提供と活用などの記述が追加されたことを受け、協会では教員支援や教材開発に積極的に取り組んできました。
12月に文科省は学習指導要領改訂に向けて中央教育審議会に諮問を行いました。現行の学習指導要領に基づく教育の成果を振り返り、今後のあり方を議論するこの時期に、第一線で活躍されている方々による議論は非常に有意義と考えます。さらに教育現場の方々には、本シンポジウムを通じて生きる力を育む教育における会計リテラシーの可能性を感じ取っていただければ幸いです。

基調講演
総合的な学習(探究)の時間が創り出す教科横断の架け橋
田村 学 文部科学省 初等中等教育局主任視学官

構造化された理解を目指す
基調講演では、文部科学省初等中等教育局主任視学官の田村学氏が「総合的な学習(探究)の時間が創り出す教科横断の架け橋」と題して、探究的な学びが学力向上に寄与することをデータで示しながら、会計教育との関連性について言及した。
田村氏はまず、2024年12月の大臣諮問において示された
・子どもたちの主体的な学びの促進
・現行学習指導要領の方向性継続とさらなる発展
・デジタル学習基盤の活用
―という審議の三つの課題を紹介。
改訂のキーワードとして「中核的な概念」と「構造化」を挙げ、上位概念の習得や深い意味の理解を促す学習指導要領の目標・内容の構造化が求められていると説明。また、教育課程の柔軟化や情報活用能力の向上、探究学習の質的向上も審議事項に含まれていることを示した。
探究学習が学力向上に貢献
現行の学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い学び」の実現には、授業改善とカリキュラム・マネジメントの両輪が不可欠だと強調。特に「深い学び」には知識の活用と発揮、アウトプット活動の質向上が重要だとした。
田村氏は「課題設定、情報収集、整理・分析、まとめ・表現の探究プロセスの中で、教科で学んだ知識が活用されれば、知識が関連付くとともに、印象にも残り確かな知識として定着する」と述べ、教科学習と探究学習の相乗効果を指摘した。
探究学習の効果は、2009年のPISA調査結果に表れているという。この調査に参加した高校1年生は、小学3年生から総合的な学習の時間を「フルに」経験した初めての世代であり、学力低下が問題視されていた中での読解力の回復のカギは探究学習にあったとみる。
また、全国学力・学習状況調査でも、探究学習に意欲的な生徒ほど各教科で好成績を収めており、2015年のOECD協同問題解決能力調査で日本が52カ国中2位となったことも、探究学習の成果だと分析した。
探究学習で深まる会計リテラシー
高校では総合的な探究の時間の開始により、課題解決型の活動を通じて「生徒たちのキャリア意識や学びの意識が変わってきている」と田村氏は指摘。会計教育と探究学習の関連については、「探究を進める中で、暮らしの中の問題を数字や経済的に捉えることは中学生、高校生にとって重要。会計リテラシーが課題解決に生きると実感できれば、教科学習の意欲も高まる」と述べ、会計教育が実社会との接点を提供し、生徒の主体的な学びを促進する可能性を示した。
最後に、教科と探究の相乗効果を高めるためのカリキュラム・デザインや、教科横断の重要性に触れ、「単元配列表の中核に総合的な学習(探究)の時間を位置付けることは理にかなっており、今後の改訂の方向性にも合致している」と述べた。
パネルディスカッション〈社会科パート〉
社会科・公民科における『会計情報の活用』授業実践と今後の展望
・樋口 雅夫 玉川大学教育学部 教育学科 教授
・岩野 清美 北九州市立板櫃中学校 講師
・淺川 貴広 都立蒲田高等学校 主幹教諭

左から樋口氏、岩野氏、淺川氏
実感の湧く教材で会計の大切さを学べる
社会科と公民科における会計情報の活用に関するパネルディスカッションでは、玉川大学教育学部教授の樋口雅夫氏をコーディネーターに迎え、北九州市立板櫃中学校講師の岩野清美氏と東京都立蒲田高校主幹教諭の淺川貴広氏がパネリストとして登壇。日本公認会計士協会が提供する教材「『会計情報の活用』教員のための授業実践ガイドブック」「授業支援パッケージ」を用いた手応えや生徒の反応を紹介し、会計教育の意義について意見交換した。
岩野氏は、中学3年の社会科公民的分野で「パン屋経営」をテーマにした授業を実施した。日本公認会計士協会提供の教材「授業実践ガイドブック」を活用し、企業活動を維持するために大切なことは何かを会計の視点から考えるのが狙いだ。
生徒たちはグループに分かれてパン1個あたりの材料費などを計算し、利益計算を行った。
「黒字と赤字のグループがちょうど半分ずつになった。売上が一番でも利益は一番ではないグループがあった他、わずかな売上の差で赤字になってしまうグループもあった。どんぶり勘定ではお店が持てないということを生徒たちが実感できる、計算し尽くされた教材だと感じた」と語った。
これに対し樋口氏は「パンの材料費などは、会計の視点から妥当な金額や数値を設定してある。この教材で授業をすれば生徒が実際にパン屋を経営しているかのような気分になれる」と、リアリティのある教材の価値を指摘した。
不正会計は何が問題?問いから始まる「公共」
教材「授業支援パッケージ」高校編の制作協力者でもある淺川氏は、「不正会計は何が問題か?」という問いから始まる探究的な授業実践を報告した。
学習前、生徒たちは「嘘はいけない」「不正をすると企業のイメージが悪くなる」といった表面的な反応を示していた。しかし意見のアウトプットを繰り返す中で、「企業に投資する人が減り、日本企業に対する信頼も低下し、ゆくゆくは日本経済そのものの減退につながる」「新たに会社を立ち上げていこうという意欲をそがれてしまう」など、より深い考察ができるようになった。
淺川氏は「企業の不祥事が業界全体、ひいては日本経済全体に悪影響を及ぼすというところまで考えられたことに感心した。会計を入口として、学びが深められると感じている」と述べた。
樋口氏は高校の「公共」において社会参画の意識や態度の育成が重視されていることに触れ、淺川氏の実践を「公共の目標に叶う授業だった」と評価した。
大学入学共通テストに会計関連用語が登場
会計教育の意義について岩野氏は「上位概念と具体的な社会事象を結びつけるのが『会計』ではないかと思う。持続可能な経営ができる社会のあり方を考えることができれば、生徒が生き方を考えることにもつながり、社会は変えていけるという視点が育つ」と語った。
淺川氏は「今後は、数学科とコラボした授業を構想したい。論理性を重視する点が会計と共通するのでは」と、他教科との連携にも意欲を見せた。
両実践に共通するのは、会計を単なる数字の計算ではなく、社会参画の手段として捉えさせる工夫だ。「会計は自分と関係ない」という生徒の先入観を払拭し、日常生活における経済活動の主体としての自覚を促すアプローチは、これからの社会科や公民科の授業の新たな方向性を示したと言える。
2025年度大学入学共通テストの「公共、政治・経済」では、「ディスクロージャー(情報開示)」や「コーポレート・ガバナンス」といった会計関連用語が登場している。樋口氏はこうした変化に触れ「社会に主体的に参画する資質・能力の育成が求められている。授業支援パッケージや授業実践ガイドブックなどの教材を使うことで、生徒のキャリア形成を促し、未来の創り手としての自覚を育むことができる。教員が会計教育を通じてさまざまな専門家や諸機関と連携することは、相互のメリットにつながるだろう」と結んだ。
パネルディスカッション〈探究パート〉
総合・探究的な学習において会計リテラシーを発揮できる場面とは
・加藤 智 文部科学省 教科調査官・愛知淑徳大学 准教授
・辻 陽介 静岡県総合教育センター 教育主査
・鶴田 光夫 日本公認会計士協会 副会長

左から鶴田氏、加藤氏、辻氏
総合的な学習(探究)の時間と会計リテラシー
総合的な学習(探究)の時間における会計リテラシーの活用をテーマにしたパネルディスカッションは今回が初めて。文部科学省教科調査官で愛知淑徳大学准教授の加藤智氏と、静岡県総合教育センター教育主査の辻陽介氏が登壇し、多彩な実践事例からその可能性を議論した。コーディネーターは、日本公認会計士協会副会長の鶴田光夫氏が務めた。
まず、加藤氏が高校における総合的な探究の時間のポイントを紹介した。学習対象を実社会に見いだし「最適解」を重視すること、小中学校の総合的な学習の時間より洗練された質の高い探究が求められることが挙げられた。その際「例えば持続可能な社会の実現といった理想を思い描くことで、現実との隔たりが明確になる。その状況を改善するために自分で課題を設定できるようにするのが教員の役割」と強調した。
辻氏からは、「今までは教員が多くの情報を発信して、子どもは受け取った情報をそのまま処理すればよかったが、今は教員から受け取った情報に対して、『これはどういうことだろう?』と生徒が自分自身に問いかけ、それによって思考を立てるという方向の学び方に変わってきている」と「学習観の転換」について話を挙げた。
採算度外視の活動が深まらない理由
コーディネーターの鶴田氏は、会計リテラシー育成の観点から「中学・高校段階ではアカウンタビリティ(説明責任)の概念を学んでほしい」と話すとともに、実現可能性や持続可能性を高める視点として、会計が総合的な探究の時間を有意義にするのではないかと指摘した。
加藤氏は会計の導入に関連して次の2つの事例を紹介した。1つは、高校生が地域支援のため弁当を提供した取り組み。地域の素材を使ったが、実際には1食あたり3000円ほどのコストがかかっていたという。2つ目は伝統行事の後継者不足を解決するため、生徒が子ども向け絵本を制作した事例。しかし費用や工面の方法を尋ねると、生徒からは明確な回答が得られなかったという。
「生徒の意欲的な取り組みとしては評価できるが、持続可能性の観点からは疑問が残る。ここに会計の視点が入れば、アカウンタビリティの概念を実践的に学べ、面白くなったはず」と語った。
会計視点で探究を深化させるには
辻氏は、会計の視点を取り入れたことで深まった探究の事例を紹介した。2人の高校生による、地場産物を活用した商品開発が、地域活性化に発展した例だ。当初、生徒たちは食品開発とその商品化を目指してPR活動を行った。しかし、活動を進める中で自分たちの取り組みが自己満足に終わっていることに気付いた。転機となったのが、地域の自営業者と交流し「会計の目がインストールされたこと」だと辻氏は振り返る。
その後、生徒たちは事業者とのコラボレーションを模索。地元のジェラート店との連携により、採算的にも持続可能な形での地域活性化を目指すようになった。「会計リテラシーが探究学習のサイクルに組み込まれたことで、生徒たちの活動が質的に変容した」と辻氏は評価する。
加藤氏からは、横浜市立南高校の生徒が考案した観光プランが紹介された。会津の日本酒づくりに高校生が参加し、20歳まで保管、成人後に楽しむ「タイムカプセル」的体験ができるというもの。地域活性化と将来の起業を目指す取り組みとして注目しているという。
加藤氏はこれらの取り組みを「オーセンティック(真正)な学び」と評価する。会計の知識をベースに、実際の社会課題に向き合うことで、より深い理解と応用力が身につくことを示唆した。
両パネリストからは、総合的な探究の時間における会計リテラシーの活用のポイントとして、公認会計士などの専門家の関与や、フィールドワーク、教室内での対話、プレゼンテーションなど会計リテラシーを活用できる場面設定の重要性も指摘された。
会計教育に関する日本公認会計士協会の取り組み
日本公認会計士協会 常務理事 梅木 典子氏

日本公認会計士協会の梅木典子常務理事が、同協会が取り組む会計教育活動について解説した。
同協会は、公認会計士法に基づく公認会計士の自主規制団体として、職業規範の整備や専門研修を通じて公認会計士の質的水準の維持・向上を図る民間法人だ。会計リテラシーの定着と会計の有用性を広めるため、20年ほど前から会計教育に取り組んできた。2022年の公認会計士法改正で会計教育が法的に位置付けられたことを受け、全国16支部と連携し活動を強化している。
協会の会計教育活動は「会計教育講座」「メディアを使った普及活動」「学校教育支援」の3つの柱で構成されている。現行の学習指導要領解説(中学校社会編・高等学校公民編)に「会計」に関する記述が加わったことを受け、授業で活用できる教材の提供や、教員の自己研さんの機会提供に力を入れている。
梅木氏は「会計とは経済活動の結果を記録して報告すること。今後も子どもたちが社会で正しい意思決定ができる力を育むため、専門家団体として学校と協力し、会計リテラシーの普及に尽力していきたい」と意気込みを語った。
アーカイブ配信のお知らせ
本シンポジウムの様子は、日本公認会計士協会HPよりアーカイブ配信にてご覧いただけます。(5月頃配信予定)
下記URLよりご確認ください。
https://jicpa.or.jp/about/activity/basic-education/event/symposium2025.html