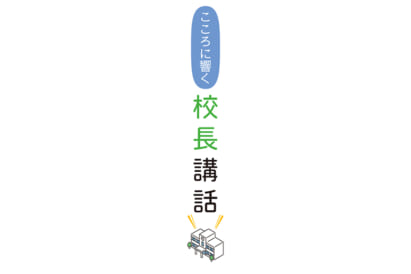名作で読む日本近代史
13面記事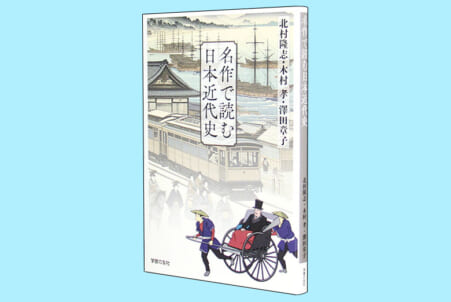
北村 隆志・木村 孝・澤田 章子 著
学歴競争など現代的課題映す
本書は、夏目漱石・徳富蘇峰から始まって宮沢賢治・細井和喜蔵に至るまでの明治・大正期の文学作品を紹介し、それぞれの作品が持つ現代的意義を論じたものである。取り上げられた33の文学作品は、詩歌・小説・随筆・社会評論・自伝・ルポルタージュなど多岐にわたっている。第1章から読み進めていくと、当時の社会状況や世相の移り変わりの様子をリアルに理解することができる。
明治維新によって、人々は自分たちを縛っていた身分制度の頸木から解放された。福沢諭吉は「学問のすすめ」で、若者たちに対して、学問を身に付け立身出世を目指すことを呼び掛けた。青雲の志を胸に立身出世していった若者たちがいた一方で、二葉亭四迷の「浮雲」の主人公のように、世渡り下手で優柔不断なために出世の機会を逸する若者もいた。ここには、現代の学歴競争の端緒の存在が見いだされるのである。
また明治・大正期は、日清戦争・日露戦争・第1次世界大戦が起こった戦争の時代でもあった。それは、富国強兵を旗印に「近代国家」を目指した国家政策であり、多くの国民が犠牲となった。田山花袋の「一兵卒」は、下級兵士から見た日露戦争の悲惨さを伝えている。
文学作品を通じて、政治・経済、教育・文化における現代的問題の起源が明治・大正期にあることを教えてくれるのである。
(1650円 学習の友社)
(都筑 学・中央大学名誉教授)