学力と評価の戦後史 学力論争・評価論争は教育の何を変えたのか
14面記事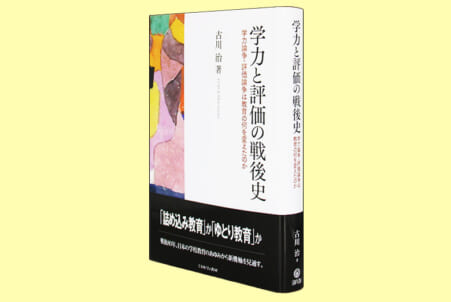
古川 治 著
80年の歩みから見通す新機軸
敗戦から80年を迎えた戦後教育は、少し振り返っただけでも、占領教育、偏向教育、道徳教育、勤評闘争、教科書問題、国旗・国歌、大規模校対策、主任制、教員の資質向上、落ちこぼれ・落ちこぼし、不登校、いじめ、教員の働き方改革等々と多事にわたるが、本書は、この戦後教育の歩みを学力論・評価論の視点から吟味・検討したものである。
3部構成で、第Ⅰ部は、戦後教育における学力・評価と著者の小・中学校時代から教職へ入職し、その後の教職人生における戦後教育との重なりについて、第Ⅱ部は、戦後の学力と学力論争について、第Ⅲ部は、戦後の評価改革と評価論争について詳述しつつ考察、課題を明らかにしている。
著者は、落ちこぼれ問題に悩み格闘していた青年教師時代から、学力と評価の第一人者の梶田叡一氏に師事。ベンジャミン・ブルームや梶田氏の学力保障と成長保障の人間教育論に学びつつ、教育委員会や大学での教員養成の経験を土台に、広範な資料を駆使し、戦後の学校教育の変遷を教育内容面から解き明かす。
折しも昨年末、文科省は現行学習指導要領が目指す「主体的な学び」に向かうことができない子どもが増加しているとして、学習指導要領の改訂を中央教育審議会に諮問した。この際、戦後80年間の学力・評価論争を振り返り検証することは、次代の教育を展望するために不可欠だろう。
(3300円 ミネルヴァ書房)
(矩)










