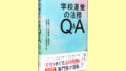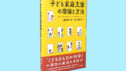早稲田教育ブックレット33 AIは教育をどう変える?可能性と課題を学際的に追究する
14面記事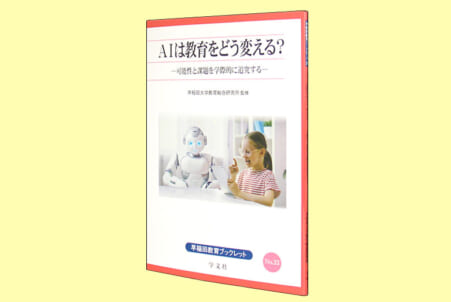
早稲田大学教育総合研究所 監修
英語学習での活用など事例に
仮名漢字変換や天気予報、カーナビ、乗換案内アプリにもAIが活用されているのだとすれば、AIはわれわれの日常生活に以前から深く入り込んでいる。だが、特に生成AIツールの登場によって、教育界への影響や活用可能性が手探りで議論されるようになった。本書も早稲田大学教育総合研究所の公募研究「情報通信技術の発展が大学教育に与える影響に関する調査・研究―オンライン授業ならびにAI利用が広がる中で教育目標・内容・方法を再考する」での議論、講演録である。
学習支援工学の専門家は、人工知能AIのできることを識別、予測、実行の三つとし、ノイズによる誤認識などの限界も指摘する。
教育行政学の専門家は、労働力不足対応として介護や医療の現場や海外では検討が進んでいるロボット導入の可能性と社会実装上の課題について提案する。
言語教育の専門家は、大学の英語教育でAIを活用している事例を報告し、AI教師の有効性について報告する。
外国語学習は、確かに翻訳ソフトの精度も急速に向上し、駅前留学やオンライン英会話の教師が人ではなくAIに変わりつつある。個別最適化したアルゴリズムに導かれ、スコアはアップするかもしれない。ただ、自動翻訳時代の英語教育の目的は何か。識別、予測、実行を旨とするAI教師には不可能なこと、そこにヒト教師の存在意義があるのだろう。
(1100円 学文社)
(元兼 正浩・九州大学大学院教授)