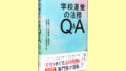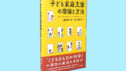脳科学はウェルビーイングをどう語るか? 最新科学が明かすふれあいとコミュニケーションの力
17面記事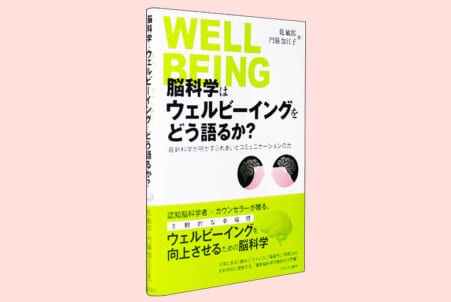
乾 敏郎・門脇 加江子 著
思いが健康に及ぼす影響示唆
世界保健機関(WHO)は、「健康」を「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態」と定義する。その「満たされた状態」が「ウェルビーイング」であり、それは、「個人の主観的な幸福感や生活の質を指す」ともいわれる。
身近な例では、痛みがある女性が、好きな男性に手を握られると、好きではない男性に握られるよりも痛みが軽減されるそうである。それは「気のせい」だと言われそうだが、必ずしもそうとはいえない。共感性の高い人同士では脳波の同期が高まって鎮痛レベルが上がるのだと脳科学では説明している。「同期」とは「わずかな時間差はあるが、ほぼ同じように変化する」ことで、脳のこのような働きを「共感脳」と呼び、この育成が大切になる。
また、疲労といえば体の疲れと思いがちだが、脳も疲労し、集中力や判断力の低下や鈍化を生む。この長期化は慢性疲労症候群につながりかねない。おおらかな気分で過ごせる人の脳は疲労への耐性が高い。主観的な思い方が即非科学的とはいえないという事実を、最近の脳科学の進歩を通して明かしてくれるのが本書の役割だ。「積善之家必余慶有」の確かさを思う。
親しみやすい図解を多く取り入れ、身近な日常生活の中にウェルビーイングを実現するヒントを提供してくれる。読後の人生が明るくなる一書だ。
(2420円 ミネルヴァ書房)
(野口 芳宏・植草学園大学名誉教授)