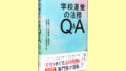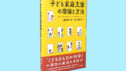学校文化の源流を探る
12面記事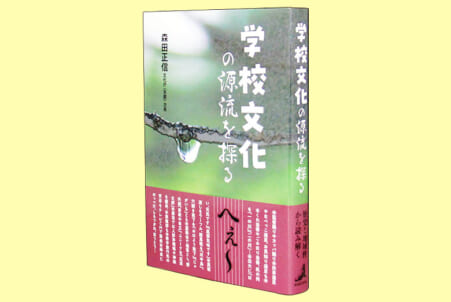
森田 正信 著
清掃、プールなど多彩に
海外で生活した子どもが日本の学校に入学すると、日本語の壁の他、給食や全校朝会、上履きなど特有の行動や決まりのような型に戸惑うことがあるので配慮が必要だ。
学校文化の起源をたどると、掃除を子ども自身で行うのは、寺で読み書きを学んでいたことと僧侶が修行として掃除をしていたことに由来する。だから今でも清掃は教育活動の一つとして教師が指導している。
学校にプールがあるのも日本特有だ。水泳の授業が最初に行われたのは大正期の大阪の学校。昭和30年に修学旅行中の小・中学生が大勢亡くなった紫雲丸事故の後、水泳の授業が取り入れられ各地でプールの整備が進んだ。運動会の発祥は、明治初期に創設された海軍兵学寮の「競闘遊戯会」。その運動会もコロナ禍や熱中症対策などで変化しつつある。
本書は学校文化の起源や変遷などを主に編まれているが、地域や学校によって異なる文化を数多く紹介している。著者は教育行政に携わる中で各地に独特な学校用語や行事があることに気付き、47都道府県全てについて学校方言や慣習、伝統行事など幅広く取材。
子どもの人権や個性の尊重、働き方改革、地球環境への配慮など、学校や教育が大きく変わろうとしている今、多様性を知ることで発想が柔軟になり、地域や学校の特色を生かした教育の創造につながっていくだろう。
(1980円 海象社)
(大澤 正子・元公立小学校校長)